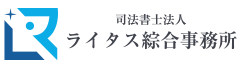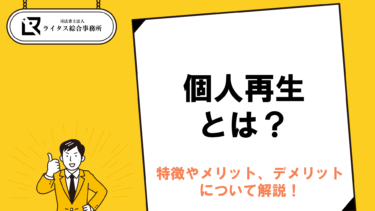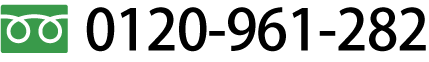個人再生を利用すれば借金が大幅に減額されるため、裁判所から認可決定が下りた時点で一安心したくなるのは当然です。
しかし、認可決定後も油断禁物なのはご存知ですか?事情次第では、せっかくの認可決定が取り消しとなるケースもあるのです。
では、取り消しを防ぐためにはどのような点に注意すべきか、司法書士の視点から詳しく解説していきます。本記事では、日々の相談業務で見聞きする具体的な事例も交えながら、実践的な対策方法についてお伝えさせていただきます。
個人再生と認可決定

個人再生は裁判所で行う手続きであるため、認可決定までには様々なハードルがありますが、決定後も気を抜くことはできません。
まずは、手続きの本質から見ていきましょう。多くの方が誤解している点や見落としがちなポイントも含めて、分かりやすく説明していきます。
個人再生とは
借金の返済が滞っている状況や、このままでは返済困難になりそうな状況から債務者を救済する制度が個人再生です。返済計画は原則3年、最長5年間で設定され、返済総額は債務総額によって異なり、5分の1(20%)から10分の1(10%)程度に減額されます。
裁判所から認可を受けた再生計画に従って完済することで、残りの債務が免除されます。
借金問題に悩む方にとって、個人再生は有効な解決策の一つです。しかし、その仕組みや手続きについて、十分に理解していない方も少なくないのではないでしょうか。 この記事では、個人再生の概要から具体的な手続き、そしてメリット・デメリットまで、[…]
個人再生のメリット・デメリット
個人再生のメリットは、マイホームを維持しながら借金を減額できる点です。
この制度を「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」といって、住宅ローンを現状どおり支払いながら、その他の借金を再生計画に則って減額させることができます。
また、自己破産とは異なり、免責不許可事由(借金の免除を認めない事情)はなく、保有財産を処分される心配がない点も、個人再生のメリットといえるでしょう。
一方で、個人再生には専門的な知識が必要になるため、司法書士や弁護士への依頼が必須です。専門家への費用負担を避けられない点はデメリットといえるでしょう。
なお、手続き費用は依頼する事務所によって異なりますが、着手金と報酬を合わせて30~50万円程度が一般的です。
再生計画案とは
再生計画案とは、減額された借金をどのように支払っていくかを裁判所や債権者に提示するために作成されます。作成については、司法書士や弁護士が債務者の収入状況や財産状況を精査したうえで作成するので、心配する必要はありません。
ただし、再生計画案を作成するには、返済原資となる収入を確認しなければなりません。給与明細や確定申告書類などの提出が必要です。
また、債権者にとっても納得できる内容でなければ認可は得られません。債権者からの異議申立てを避けるためにも、安定した返済を継続できることを証明する必要があります。
認可決定までの流れ
個人再生の手続きは、司法書士や弁護士への相談から始めましょう。
直近の収入証明や借金の状況を示す資料を揃え、裁判所に個人再生の申立てを行います。裁判所は、提出された申立書と再生計画案について審査を開始します。
申立て後、裁判所から債権者に対して債権届出の催告が行われ、届出期間が経過すると最終的な債権額が確定。この間、再生債務者は「履行テスト」といって、実際に返済が継続できるかを、毎月積み立てを行いながら裁判所に確認されることになっています。
その後、小規模個人再生の場合は、債権者から一定割合以上の反対がなければ裁判所から認可決定が下されます。認可を得るまでには数か月を要するのが一般的です。
\LINEで気軽に相談可能!/
認可決定後に取り消しになることはあるのか?

個人再生の認可決定は、必ずしも手続き完了を意味するものではありません。その後は再生計画に則った支払いを継続する必要があり、返済が滞るようであれば認可決定が取り消されることもあります。
以下では、認可決定の取り消しについて詳しく見ていきましょう。
認可決定後でも取り消しの可能性はある
裁判所から出された認可決定は絶対的なものではありません。返済が滞ってしまい、債権者から取り消しの申立てをされれば、裁判所の判断により取り消されることがあります。
とはいえ、認可決定後の取り消しは過去の司法統計を見てもそれほど多くはありません。直近の2023年度の統計では0件、2022年度の統計でも0件となっています。
しかし、過去にまったく取り消しがなかったわけではないため、安心しきるのは禁物です。
取り消しになるとどうなるのか
取り消し決定が確定すると、借金の減額は無効となります。債権者からの請求も再開され、最悪のケースでは強制執行によって財産を差し押さえられる危険も出てくるでしょう。
また、取り消し後は遅延利息なども含めて請求されることになり、返済負担は当初よりも重くなります。債権者との信用は失われてしまい、個別の交渉にも応じてもらえないとなれば、最終的には自己破産しか選択肢がなくなってしまうのです。
取り消しになる事由
認可決定後に再生計画の取り消しとなるのは、主に以下2つの事由からになります。
まず1つ目は、再生計画が不正な方法で成立していたことが判明した場合です。
不正な方法とは、具体的には虚偽申告です。収入や財産状況について事実と異なる申告をした場合、取り消しになるおそれがあります。財産隠しも同様で、預貯金や不動産などの財産を意図的に申告から除外した場合も取り消しの対象です。
2つ目は、債務者が再生計画を履行できなかった場合です。返済計画に基づく支払いが滞った場合も取り消しとなる可能性があります。正当な理由のない支払い遅延が続くと、債権者から取り消しの申立てをされることになります。
取り消しを避けるための対策
取り消しを避けるもっとも有効な方法は、無理のない再生計画案を立てることです。
事前に司法書士や弁護士との綿密な打ち合わせを通じて、目先だけでなく将来にわたって実現可能な返済計画を立てることが重要です。そのためにも、収入状況や将来的な見通しについても、正確な情報提供を心がけましょう。
なお、認可決定後に財産状況に変化があった際は速やかな報告も欠かせません。収入が増加した場合はもちろん、予期せぬ支出が発生した場合なども、担当してくれた司法書士や弁護士に相談することをお勧めします。
必要な対処を司法書士や弁護士がしてくれるため、取り消しリスクを避けながら、返済を継続することができるでしょう。
\LINEで気軽に相談可能!/
取り消し決定後の対応

では、もし認可決定が取り消されてしまった場合、どのような選択肢があるのでしょうか?以下にて具体的に説明していきます。
不服申し立ての権利はある
取り消し決定に納得がいかない場合、即時抗告という形で不服申立てが可能です。
ただし、申立て期間には制限があるため、迅速な対応が求められます。裁判所からの通知を受け取った日から2週間以内(民事再生法9条)に行わなければなりません。
再度の個人再生申立ての可能性
個人再生は、原則として2回目の申立ても可能となっています。たとえば、認可決定後、再生計画に則って支払いを継続している最中であっても、再度申立てすることは可能です。
ただし、給与所得者等再生による認可決定を得ていた場合は、認可決定から7年間は再度の申立てができなくなっています。また、短期間での2回目の申立てとなると、裁判所の審査が厳しくなる他、債権者からの同意を得るのが難しくなるため注意が必要です。
自己破産への移行
どうしても再生計画による返済を継続できないのであれば、自己破産もやむを得ません。
しかし、自己破産は一定の現金や生活必需品を除き、高価な財産等は処分対象となり、債権者への配当に充てられてしまうため、手放さなければならないものが多くあります。
「自己破産しか選択肢がない」なんてことにならないように、司法書士や弁護士には現況を正直に伝えるようにし、再生計画を綿密に立てるよう心がけてください。
\LINEで気軽に相談可能!/
まとめ
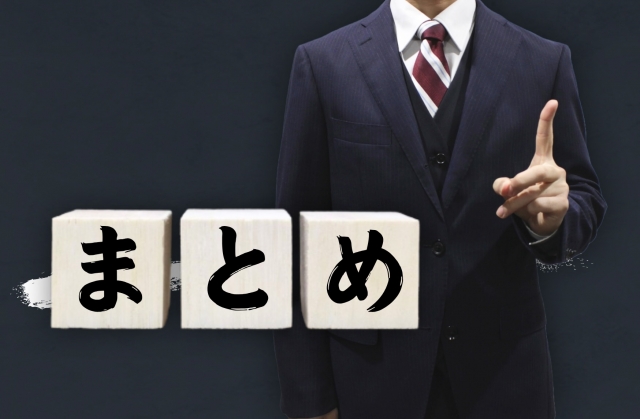
個人再生は借金問題を根本から解決させられる手続きですが、裁判所からの認可決定後も気を抜くことはできません。取り消しリスクを意識した計画的な返済継続が重要です。
当事務所では個人再生に関する相談を随時受け付けています。司法書士や弁護士による適切なサポートを受けることで、より安全確実な債務整理を進めることができます。一人で悩まず、まずは司法書士や弁護士に相談されてはいかがでしょうか。
借金返済にお困りなら今すぐご相談ください
当事務所は任意整理・個人再生・自己破産に対応しています(司法書士業務の範囲内に限る)。どの手続きが良いか分からない場合、ご依頼者様の状況を見てご提案しますのでご安心ください。
当事務所は任意整理・個人再生・自己破産に対応しています(司法書士業務の範囲内に限る)。どの手続きが良いか分からない場合、ご依頼者様の状況を見てご提案しますのでご安心ください。