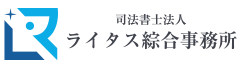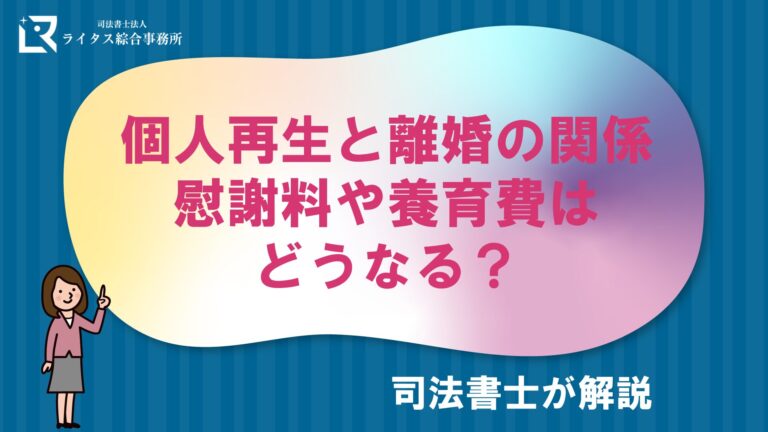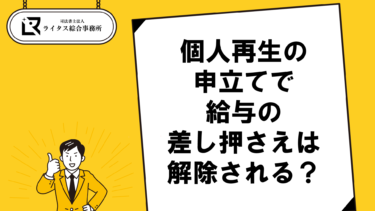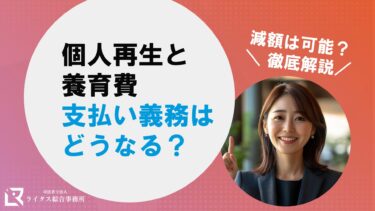借金が原因で離婚を考える方、離婚後の生活再建で借金に悩む方が多くいます。司法書士事務所には日々そんな相談が寄せられます。「養育費は払えるのか」「慰謝料はどうなるのか」といった不安な気持ちは当然のことでしょう。
借金の整理方法として個人再生という選択肢がありますが、離婚と同時期となると、考えるべきポイントは複雑になります。今回は、個人再生と離婚が重なったケースでの影響や注意点を解説します。
個人再生と離婚の関係

個人再生と離婚は、手続きにおいてまったく別物なので、相互関係のようなものはありません。しかし、いずれも金銭に関する問題であるため、複雑な影響を及ぼし合うのも事実です。以下では、具体的な影響と注意点を見ていきましょう。
離婚そのものは個人再生に影響しない
離婚を理由に個人再生の申立てが却下されることはありません。裁判所は申立人の生活状況や返済能力を審査しますが、婚姻状態は審査の判断材料にはなり得ないのです。
ただし、離婚による世帯収入の変化が申立ての重要なポイントとなります。世帯収入が大きく減少する場合、返済計画の実現可能性に疑問が生じる可能性があるからです。
特に共働き世帯が別居や離婚で片働きになった場合、月々の返済可能額に大きな影響が出ます。「離婚後の収入で返済できるか心配」という声をよく耳にしますが、申立て前後で世帯収入に大きな変化がある場合、裁判所への報告は慎重にならざるを得ないでしょう。
離婚による財産分与で清算価値が増え最低弁済額が増加することがある
財産分与(離婚に伴う財産の分配)は個人再生における清算価値(申立時点での保有財産)に大きな影響を与えます。
財産分与で受け取った金額や資産は清算価値として計算されるため、清算価値が増えると債権者への最低返済額も増加する仕組みです。逆に財産分与で支払う側になった場合でも、過度な支払いは清算価値に組み込まれることがあります。
具体的な事例を挙げると、離婚時に配偶者から退職金の一部として500万円の財産分与を受けた場合、個人再生の申立てでこの金額は清算価値に含まれます。結果として債権者への返済額が増える点に注意が必要です。
別のケースでは、離婚調停中の方が個人再生を申し立てたものの、財産分与額が確定していないため手続きが一時中断となりました。財産分与の内容が個人再生に及ぼす影響を慎重に検討する必要があったからです。
実務上の対応としては、離婚協議の段階から個人再生を視野に入れた財産分与の妥当性について、専門家と検討すべきと言えるでしょう。
離婚後の転居と住宅ローン特則の利用制限
住宅ローン特則は、マイホームを維持しながら借金を整理できる、個人再生ならではの制度です。ただし利用には条件があり、対象の不動産に住み続けている必要があります。
離婚によって転居が予定されているのであれば、住宅ローン特則の利用は難しくなってしまうため、離婚時にマイホームをどうするのか、といった点が重要になってきます。
典型的なケースとしては、夫婦共有名義のマンションについて、離婚を機に妻が子どもと転居し、夫が居住を継続するパターンがあります。この場合、夫は住宅ローン特則を利用できる可能性がありますが、転居した妻は特則を使えなくなります。
その他にも、共有名義の解消や、妻が保証人であれば新たな保証人について、住宅ローン債権者への返済のリスケジュールなど、様々な問題が生じることになります。
さらに、離婚時の財産分与で配偶者に持分を譲渡する場合も要注意です。譲渡後の持分比率によっては、清算価値に大きな影響を与えることになります。
上述したとおり、清算価値が膨らんでしまうと、個人再生による返済額も膨らんでしまうため、どのように対処すべきかについては専門家の意見を仰ぐようにしてください。
「毎月の住宅ローン返済に追われながら、他の借金返済にも苦しむ」という状況から抜け出す道があるのをご存知でしょうか。 債務整理の一つに、借金を大幅に減額してくれる個人再生という手続きがあります。その個人再生にある住宅ローン特則と呼ばれる[…]
\LINEで気軽に相談可能!/
個人再生が離婚後の慰謝料に与える影響
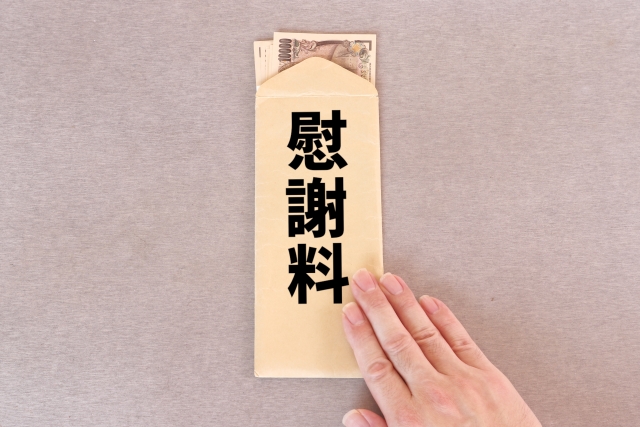
離婚問題における重要な要素である慰謝料について、個人再生手続きとの関係を説明します。
慰謝料の種類による取り扱いの違い
慰謝料には法的性質の異なる種類があり、個人再生での扱いも変わってきます。不法行為による損害賠償、財産分与としての慰謝料、生活扶助としての慰謝料など、性質によって取り扱いが異なることがあります。
実例を挙げると、配偶者の不貞行為による慰謝料300万円について、不貞の事実を認識しながら継続していた場合は悪意による不法行為とされ、非減免債権として扱われました。一方、一時的な過ちで関係を解消した場合は再生債権として扱われた事例もあります。
また生活扶助としての慰謝料は、離婚後の生活保障という性質から非減免債権となるケースが多いです。財産分与に含まれる慰謝料も同様の扱いを受けます。
そもそも慰謝料の有無についても、個人再生の取扱上問題になるケースも多いため、個々の状況に応じて適切な判断を専門家にしてもらうのが良いでしょう。
再生債権として扱われる慰謝料
通常の離婚における慰謝料は、重大な過失や悪意がない限り再生債権として減額対象です。夫婦関係の破綻による慰謝料がこれに該当します。
具体的な判断事例としては、性格の不一致による離婚で200万円の慰謝料が発生したケースがあります。双方に重大な非がなく、話し合いによる解決だったため再生債権として認められ、他の借金と同様に減額対象となりました。
ただし慰謝料を受け取る側の立場では、手続き開始前に発生した慰謝料債権は清算価値として考慮される場合があるので注意が必要です。実務では、離婚時期と個人再生申立てのタイミングが重要な要素となります。
調停や裁判で慰謝料額を決める際も、支払い側の個人再生申立ての可能性を考慮する必要があるでしょう。実際の相談では、再生債権として扱われる可能性を踏まえた金額設定を提案することも少なくありません。
手続き後に発生した慰謝料への対応
個人再生手続き開始後に発生した慰謝料については、新たな債務として随時弁済が必要になります。減額対象とはならず全額支払いが求められるのです。
実務経験では、個人再生申立て後に離婚調停が始まるケースもあります。この場合、調停で決まる慰謝料は新規債務として扱われ、返済計画とは別枠での支払いになります。
ただし、分割払いの場合は特に注意が必要です。返済計画に組み込めない毎月の支払いとなることもあります。再生計画に支障が出る可能性があるため注意しましょう。
\LINEで気軽に相談可能!/
個人再生が離婚後の養育費に与える影響

子どもの福祉に直結する養育費については、個人再生手続きでも特別な配慮がなされています。以下では、個人再生が離婚後の養育費に与える影響について見ていきましょう。
養育費は非減免債権として扱われる
養育費は子どもの健全な成長のために必要不可欠な費用です。法律上も子どもの福祉を最優先する原則から、個人再生による減額対象とはなりません。
さらに重要なのは将来の養育費支払いについてです。養育費は子どもが成人するまで継続する債務であり、個人再生後も定期的な支払い義務は変わりません。
養育費を受け取る側への影響
養育費を受け取る立場からすると、相手方の個人再生は生活設計に大きな影響を与えかねません。返済能力低下による支払い遅延リスクが高まるためです。
実務では次のような対応策を提案しています。まず、養育費の支払い確保のため、給与差押えや口座引き落としなど、確実な回収方法を検討します。
また、相手方が個人再生を理由に養育費の減額を求めてくるケースも少なくありません。
この場合、子どもの利益を守る観点から、安易な減額に応じないのも大切です。調停での解決を目指す場合は、相手方の支払い能力を見極めつつ、子どもの生活水準を維持できる金額を設定するよう心がけましょう。
養育費支払い能力確保のためのポイント
個人再生後も養育費を確実に支払い続けるには、安定した収入基盤が欠かせません。現在の職場での継続就労や、必要に応じて収入増加策を検討することが重要です。
個人再生の返済期間は原則3年間と限られているのに対し、養育費は子どもが成人するまで支払われるべきものです。しかし言い換えれば、個人再生の返済が終わりさえすれば、その後は十分な生活費の確保、場合によっては貯蓄も可能になるでしょう。
支払いが終了するまでの期間は業務量を増やすなど、養育費支払いを最優先に考えながらも、収入増加に向けた資格取得や技能向上も視野に入れるのがおすすめです。
\LINEで気軽に相談可能!/
まとめ

個人再生と離婚の問題は、法律上も生活面でも複雑な関係性を持っています。財産分与や住宅ローン特則、慰謝料、養育費など、重要な検討事項が山積みです。
当事務所では日々さまざまなケースに対応していますが、状況は一つ一つ異なります。
一人で悩まず、まずは専門家に相談されることをおすすめします。専門家のサポートを受けることで、解決への糸口が見つかるでしょう。
借金返済にお困りなら今すぐご相談ください
当事務所は任意整理・個人再生・自己破産に対応しています(司法書士業務の範囲内に限る)。どの手続きが良いか分からない場合、ご依頼者様の状況を見てご提案しますのでご安心ください。
当事務所は任意整理・個人再生・自己破産に対応しています(司法書士業務の範囲内に限る)。どの手続きが良いか分からない場合、ご依頼者様の状況を見てご提案しますのでご安心ください。