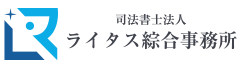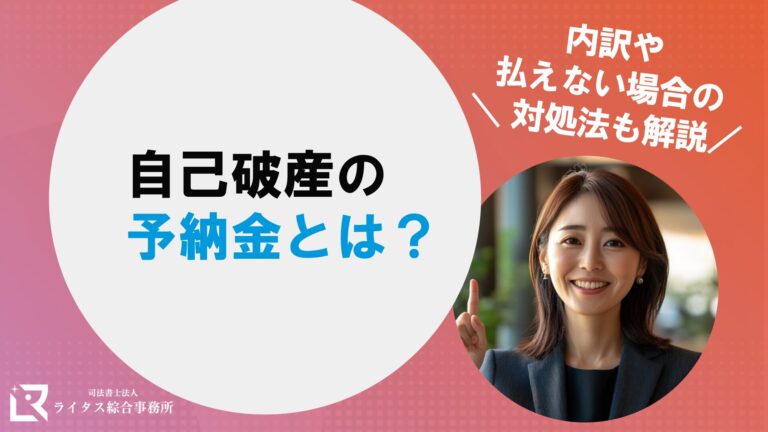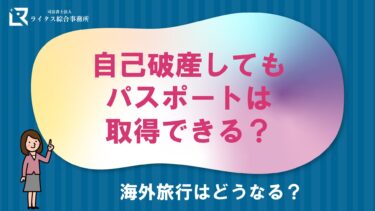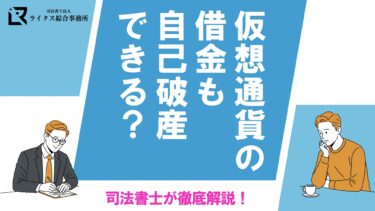生活費の工面さえ困難な状況で、破産手続きの予納金支払いに悩む方は多いでしょう。破産手続きにはさまざまな費用がかかりますが、特に予納金は手続きの最初の重要な支出です。
この記事では予納金の仕組み、具体的な金額、支払えない場合の対処法まで、実務経験をもとに分かりやすく解説します。
自己破産の予納金とは?

自己破産を申立てる際に避けては通れないのが予納金です。予納金は裁判所に支払う手続きの基本経費のようなものです。予納金の仕組みを知ることで、破産手続きへの不安も和らぐでしょう。
ここでは、予納金の詳細や実際の費用について詳しく見ていきましょう。
自己破産の予納金の概要
自己破産手続きを始めるには予納金(よのうきん)が必要です。詳しくは後述しますが、官報掲載費用や、破産管財人への費用(報酬)として、裁判所に納めなければなりません。
自己破産の手続きは、同時廃止事件と管財事件(少額管財事件)に分けられるのですが、破産管財人が選任される管財事件では予納金が20~50万円と高額になるケースもあるため注意が必要です。
予納金を支払わなければ、手続きを完結させることはできないため、申立て前の段階で準備しておくことが重要です。
予納金の内訳
予納金は複数の費用から構成されています。まず基本となるのは官報公告費用です。これは債権者に破産手続きの開始を知らせるために官報に掲載するもので、法律で定められた重要な手続きです。
郵便切手代も予納金の一部として表現することがあります。金額は申立てをする裁判所によっても若干異なりますが、数千円程度を納める必要があります。
債権者への書類送付に使用され、債権者数が多いほど費用も増加します。最近は電子連絡も増えていますが、法的通知は依然として郵便で行われることが一般的です。
破産管財人が選任される場合も予納金が必要です。破産管財人は裁判所が選任した弁護士が担当し、債務者の預貯金や不動産、生命保険などの財産を調査・管理します。
予納金を支払うタイミングと方法
予納金は申立書類を提出してから1か月以内に支払う必要があります。支払い方法は、主に裁判所窓口での現金払いか、専用の振込用紙による銀行振込のどちらかです。
支払い期限を過ぎると手続きが自体が棄却されることもあり注意が必要です。また基本的に予納金の分割払いは認められていません。一括で支払う必要があるため、計画的に準備しておく必要があります。
なお、各裁判所によって予納金の取り扱いには若干の違いがあります。支払いのタイミングや具体的な金額などは、事前に管轄の裁判所に確認しておくとスムーズに進められます。特に地方の裁判所では独自のルールがある場合もありますので、注意が必要です。
\LINEで気軽に相談可能!/
自己破産の予納金の目安

破産手続きの種類によって予納金の金額は大きく異なります。この金額は、財産状況や債権者の数、手続きの複雑さなどの要素によって決まります。
具体的な金額の目安をあらかじめ知っておくことで、より現実的な破産計画を立てることができるでしょう。
同時廃止事件の場合
財産がほとんどない状態で破産を申立てることを「同時廃止事件」と呼びます。破産管財人による財産調査が必要ないため、最も予納金が少なく済む手続きです。
高額な財産を保有していない方が破産申立てをする場合、多くは同時廃止事件に該当します。必要な予納金は1万円から2万円程度となっています。
主な支出は官報公告費用と郵便切手代です。債権者の数が多いと郵便切手代が増えるため、どの程度必要になるかは裁判所に確認しておきましょう。
自己破産の同時廃止とは、破産手続きが開始されるものの、債権者への分配が不要な場合に手続きが速やかに終了する方法です。 多くの人がこの制度に直面する際、複雑な手続きや費用の不安を抱えているでしょう。「手続きは面倒で、費用も高いのでは?」[…]
管財事件の場合
破産管財人による本格的な財産調査が必要となる管財事件では、予納金も高額になります。換価可能な財産がある場合や事業を営んでいた個人の破産は管財事件となる可能性が高く、不動産や有価証券、高額な預貯金があれば必然的に管財事件として扱われるでしょう。
通常管財事件の場合、必要な予納金は最低でも50万円以上となり、これには破産管財人の報酬や調査費用、配当手続きの経費が含まれています。
手続き期間が長期化するため、精神的な負担も考慮が必要です。破産管財人は債務者の全財産を調査し、換価・配当する権限を持ちます。
「自己破産の管財事件」とは、借金を抱えて支払いが困難になった場合に、裁判所が管財人を選任し、財産の整理や配分を行う手続きです。 この手続きは、通常の自己破産よりも複雑で時間がかかることが多いため、手続きを進める前に流れや費用について把[…]
少額管財事件の場合
少額管財事件は管財事件の簡易版として位置づけられ、10~20万円程度の予納金が一般的です。財産規模が小さく、調査項目も限定的な場合に適用される手続きで、効率化と費用負担の軽減を目的としています。
ただし、裁判所によっては弁護士への依頼が条件であることも多く、予納金とは別に弁護士費用も必要です。しかし、通常の管財事件と比べると負担は大幅に軽減されます。弁護士費用も分割払いに対応する事務所が増えており、総合的な費用負担を抑えることが可能です。
\LINEで気軽に相談可能!/
自己破産の予納金が払えない場合の対処法

自己破産の手続きには予納金が必要ですが、予納金を支払えない場合でも諦める必要はありません。状況に合わせた対処法がいくつか用意されており、これらを活用することで予納金の負担を軽減できます。
法テラスを利用する方法
法テラス(日本司法支援センター)では、一定の収入基準以下の方や生活保護受給者に対して予納金の立替制度を提供しています。立替金は月々の分割払いで返済でき、収入に応じて返済額が設定されるため、無理のない支払計画を立てやすい制度です。
返済期間も長期間認められており、経済的負担を軽減できます。利用には収入等に関する証明書類が必要です。書類の準備から申請手続きまで司法書士や弁護士が全面的にサポートしてくれる体制が整っています。
裁判所へ分割払いを相談する方法
裁判所にもよりますが、分割払いを認めてくれるケースも存在します。しかし、すべての裁判所で分割払いに応じてくれるわけではないため、別の方法も検討しなければなりません。
実務上そういった場合は、申立てそのものを保留し、その期間中に予納金をプールするという方法を取るのが一般的です。弁護士や司法書士が手続きに介入していれば、債権者からの催促が本人に対して行われることは基本的にありません。
債権者から専門家に連絡が入った場合でも、「申立て準備中」と伝えることで、債権者側も納得するケースがほとんどです。ただし、執拗な取り立ては行われないものの、専門家の介入は債権者からの法的手続きの着手まで止めることはできません。
弁護士や司法書士への相談を活用する方法
破産手続きに詳しい弁護士や司法書士に相談することで、予納金の負担を抑える方法が見つかる可能性があります。手続きの選択や法テラスの利用方法など、個々の状況に合わせた最適な解決策を提案してもらえるでしょう。
最近は費用の分割払いに対応する事務所も増えており、初回相談が無料の事務所も多いので気軽に相談できます。弁護士や司法書士との相談では、予納金以外の費用や手続き全般についても確認することができます。
さらに、破産以外の債務整理方法(任意整理や個人再生など)についても検討でき、将来の生活再建を見据えた総合的なアドバイスを得られることが、専門家相談の大きな利点です。
\LINEで気軽に相談可能!/
まとめ

自己破産の予納金が負担になっても、さまざまな解決策があります。専門家からの適切なアドバイスを活用することで、状況に合った対処法が見つかります。
破産手続きに詳しい弁護士に相談すれば、個々の状況に応じた最適な選択肢を提案してもらえるでしょう。多くの弁護士事務所では分割払いや初回無料相談に対応しており、破産以外の債務整理方法も含めた総合的な解決策を検討できます。
当事務所では自己破産の予納金に関する相談も随時受け付けています。司法書士業務の範囲内で債務整理全般に対応しているので、借金問題で悩む方は、お気軽にご相談ください。
借金返済にお困りなら今すぐご相談ください
当事務所は任意整理・個人再生・自己破産に対応しています(司法書士業務の範囲内に限る)。どの手続きが良いか分からない場合、ご依頼者様の状況を見てご提案しますのでご安心ください。
当事務所は任意整理・個人再生・自己破産に対応しています(司法書士業務の範囲内に限る)。どの手続きが良いか分からない場合、ご依頼者様の状況を見てご提案しますのでご安心ください。