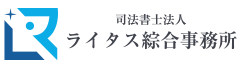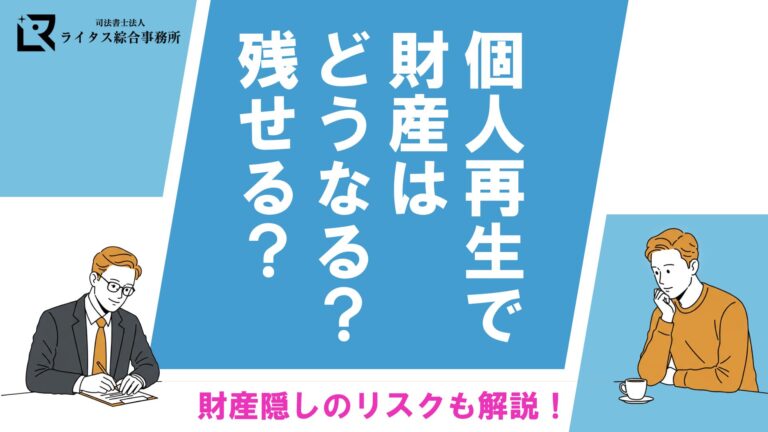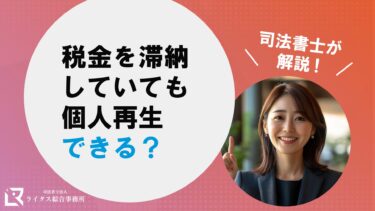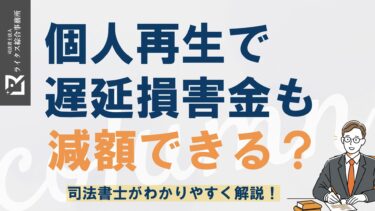借金問題が深刻化した際に選択肢となる「個人再生」。自己破産とは異なり、収入を維持しながら借金を大幅に減額できる債務整理方法として注目されています。
今回は個人再生における財産の取り扱いについて、何が残せて何が処分される可能性があるのか、また財産調査の実態や財産隠しのリスクについても詳しく解説していきます。
個人再生における財産の取り扱い

個人再生は自己破産と異なり、基本的に財産を維持したまま債務の整理を行える制度です。しかし、全ての財産が無条件で手元に残せるわけではなく、いくつかの注意点があります。
個人再生では「清算価値保障原則」という考え方が重要になります。債権者の利益も考慮した上で、適切な返済計画を立てる必要があるのです。では具体的に、個人再生において財産がどのように扱われるのか見ていきましょう。
個人再生で財産の取り扱いはどうなる?
個人再生では、原則として財産を処分する必要はありません。これは自己破産と大きく異なる点で、個人再生の大きなメリットと言えるでしょう。
ただ、担保権が付いている財産については注意が必要です。例えば住宅ローンの残っている家や、ローン返済中の車などは、返済が滞れば担保権者によって引き上げられることがあります。
もう一つ重要なのが「清算価値保障原則」です。これは、債権者が自己破産した場合に得られる金額よりも多くの返済をしなければならないという原則です。財産の清算価値が借金額を上回ると、再生計画が認可されない可能性もあります。
住宅については「住宅ローン特則」という制度を利用することで、住宅ローンが残っている家を手元に残すことが可能です。通常の個人再生では住宅ローンも減額対象になりますが、この特則を使えば住宅ローンを除外して他の債務だけを減額できます。
「毎月の住宅ローン返済に追われながら、他の借金返済にも苦しむ」という状況から抜け出す道があるのをご存知でしょうか。 債務整理の一つに、借金を大幅に減額してくれる個人再生という手続きがあります。その個人再生にある住宅ローン特則と呼ばれる[…]
個人再生で処分される可能性のある財産
個人再生では基本的に財産を手元に残せますが、いくつかのケースでは処分される可能性があります。特に注意が必要なのは、担保権が設定されている財産です。
高額な財産を所有している場合は、「清算価値保障原則」により財産の一部を処分する必要がある場合もあります。例えば、複数の不動産や高級車、高額な美術品などを所有している場合、清算価値が借金額を大きく上回ると、再生計画が認可されない可能性があります。
意外と見落としがちなのが、保険解約返戻金や退職金の一部も財産として認定される点です。生命保険の解約返戻金や将来受け取る予定の退職金も財産に含まれ、場合によっては処分対象となる可能性があります。特に解約返戻金が高額な保険に加入している場合は注意が必要です。
個人再生で残せる財産
個人再生の大きな魅力は、多くの財産を手元に残せる点にあります。特に担保権が付いていない財産は基本的に手元に残すことができます。
例えば、完全に支払いが終わった車や不動産が担保権なしであれば、個人再生手続きで換価されることはありません。ローンの完済済みの車や相続で取得した不動産などは、そのまま使い続けることが可能です。
生活に必要な家財道具や一般的な家電なども、手元に残すことができます。テレビ、冷蔵庫、洗濯機などの家電製品や、日常生活に必要な家具、衣類などは処分されません。
先ほども触れましたが、住宅ローン特則を利用することで、住宅ローンが残っている家も手元に残すことが可能です。マイホームを守りたい方にとって、個人再生は非常に有効な選択肢と言えるでしょう。
\LINEで気軽に相談可能!/
個人再生の財産調査とは?

個人再生を申し立てる際には、必ず財産調査が行われます。この調査は手続きの公正さを保つために重要なステップであり、適切な再生計画を立てるためにも必要不可欠です。
財産調査ではどのようなことが行われ、どんな資料が必要になるのでしょうか。また、調査の結果によって再生計画にどのような影響があるのかについても見ていきましょう。
財産調査の概要
個人再生の申し立てにおける財産調査は、再生計画を実行するために不可欠な手続きです。申立人は、自分の所有する不動産や預貯金、車、保険、退職金などの資産を詳細に報告します。
再生計画は、借金の一部を減額して返済することが目的ですが、清算価値保障の原則により、申立人が持っている財産をすべて売却した場合に得られる金額(清算価値)以上の返済はしなければならないとされています。つまり、個人再生で免除される金額は、財産を処分した場合に得られる価値より少なくてはならないというルールです。
最低限支払うべき弁済額を決定するために財産調査が行われるため、適切な財産開示が求められます。不正確な申告が発覚すると、手続きが不許可となる可能性もあるため、正確な報告が重要です。
財産調査の目的と範囲
個人再生の財産調査は、債務者の財産状況を明らかにし、再生計画の策定に役立てることを目的としています。
調査範囲は多岐にわたり、預貯金や有価証券、不動産などの明らかな財産だけでなく、生命保険の解約返戻金や将来受け取る可能性のある相続財産なども対象です。最近譲渡した財産についても調査対象となる場合があり、不当な財産移転がなかったかどうかも確認されます。
財産調査では、安定した収入があるかどうか、生活費はどの程度必要か、再生計画に基づく返済が可能かどうかなど、再生計画が現実的であるかどうかを調査していきます。
財産調査の手続きと資料提出
財産調査の手続きでは、まず財産目録の提出が必要です。この財産目録には、保有している全ての財産の種類や金額を記載します。裁判所はこれをもとに調査を行うのです。
資料提出には、通帳や登記簿謄本、クレジットカードの利用明細など、多岐にわたる書類が必要になります。預金通帳は過去数ヶ月分のコピーが求められることが多く、不動産を所有している場合は評価額を示す資料も必要です。車や高価な動産を所有している場合は、その価値を証明する資料も求められます。
財産調査では不正の有無も調査対象。特に不当な財産移転がなかったかどうかが重点的に調査されます。例えば、特定の債権者だけに返済したり、財産を第三者に移したりするような行為が発覚すると、手続きが認められない可能性もあります。正確かつ誠実な申告が求められるのです。
\LINEで気軽に相談可能!/
個人再生で財産隠しするリスク

個人再生手続きにおいて、財産を隠すことは厳に慎むべき行為です。財産隠しをするとどのようなリスクがあるのか、法的にどのような影響があるのか、再生計画にどのような影響があるのかを詳しく見ていきましょう。
財産を隠すリスク
財産隠しは、個人再生手続きにおいて厳しく禁止されています。裁判所に提出する財産目録に財産を記載しなかったり、財産を他人名義に移したりするような行為は、全て財産隠しとみなされるのです。
財産隠しが発覚すると、再生手続きが廃止される可能性があり、最悪の場合、詐欺罪に問われる可能性もあります。裁判所に対して虚偽の申告をすることは犯罪行為であり、刑事罰の対象となることを理解しましょう。
財産隠しの結果と法的影響
財産隠しが発覚した場合、単に手続きが認められないだけでなく、詐欺罪に問われる可能性もあります。裁判所に対する虚偽申告は犯罪行為であり、罰金や懲役などの刑事罰が科される可能性があるのです。
財産隠しは一時的に財産を守るように見えても、長期的には大きなリスクを伴います。むしろ正確な財産状況を申告し、法的な手続きの中で財産を守る方法を模索するほうが賢明といえるでしょう。
財産隠しによる再生計画への影響
後から財産隠しが発覚すると、再生計画が取り消されるリスクがあるため注意が必要です。再生計画が取り消されると、減額された債務が元に戻り、さらに延滞利息なども加算される可能性があります。
財産隠しがばれると、債権者に損失を与えることになります。個人再生は債権者の利益も考慮した制度であり、債権者に不当な損失を与える行為は認められません。債権者の信頼を損なうことで、和解や任意整理などの他の解決策も困難になる可能性があります。
重要なのは、正確な財産状況をもとに再生計画を作成することです。確かに全ての財産を申告すると返済額が増える可能性はありますが、それは法律に基づいた公正な計算によるものです。むしろ、専門家と相談しながら合法的に財産を守る方法を探るほうが、長期的には有利に働くでしょう。
\LINEで気軽に相談可能!/
まとめ

個人再生では、自己破産と異なり基本的に財産を手元に残せることが大きなメリットです。特に住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを守りながら他の借金を減額できる可能性があります。
ただし、担保権が付いている財産や高額な財産については注意が必要です。場合によっては処分が必要になることもあります。財産調査では正確な申告が求められ、不正が発覚すると手続きが認められないこともあり、注意が必要です。
何より重要なのは、財産隠しのようなリスクの高い行為は避け、専門家のサポートを受けながら適切な手続きを進めることです。当事務所では個人再生に関する相談も随時受け付けています。借金問題で悩んでいる方は、一人で抱え込まずに、まずは専門家に相談されてみてはいかがでしょうか。
借金返済にお困りなら今すぐご相談ください
当事務所は任意整理・個人再生・自己破産に対応しています(司法書士業務の範囲内に限る)。どの手続きが良いか分からない場合、ご依頼者様の状況を見てご提案しますのでご安心ください。
当事務所は任意整理・個人再生・自己破産に対応しています(司法書士業務の範囲内に限る)。どの手続きが良いか分からない場合、ご依頼者様の状況を見てご提案しますのでご安心ください。