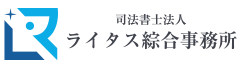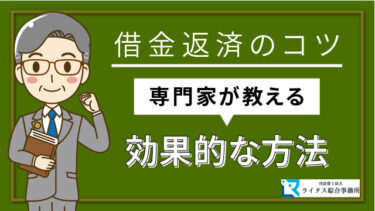借金問題でお困りの方のために、法的な解決手段としてまず「個人再生」という制度があります。その中でも、生活再建を実現する制度として「給与所得者等再生」と「小規模個人再生」というものが存在します。
両制度は、利用できる条件や手続きの流れに大きな違いがあり、詳細を把握した上で、自分の状況にあった制度を選ぶことが大切です。今回は、誰にどの制度が適しているのか、具体的な要件から選び方まで詳しく解説していきます。
給与所得者等再生とは?

生活と仕事を両立させながら、借金問題を法的に解決する手段が「給与所得者等再生」制度です。民事再生法に基づいた債務整理手続きで、安定した収入のあるサラリーマン向けの制度と言えるでしょう。
給与所得者再生=個人再生の一形態
給与所得者等再生制度は、個人再生手続きの一種です。この制度の利用者は、主に毎月給与収入があるサラリーマンやパート、アルバイトの方を対象としています。
一般的に、債務整理では全額返済が原則ですが、給与所得者等再生では、債務の一部免除を受けながら残りの債務を分割で返済していくことができます。
通常の個人再生と比べると手続きが簡素で、サラリーマンにとってはメリットの大きい制度です。債権者からの異議申し立ても少なく、比較的スムーズに債務整理を進められます。
住宅ローン特則を活用することで、住宅を維持しながら借金を整理できる点が特徴
給与所得者等再生における大きな特徴の一つが、住宅ローン特則(住宅資金貸付債権に関する特則)です。住宅を手放すことなく債務整理を行えるというのは、かなり大きなメリットでしょう。
住宅ローンの返済を継続しながら、住宅ローン以外の借金(クレジットカードやキャッシング等)の債務整理が可能です。住宅ローンについては、これまで通りの返済を続けることができます。
つまり、生活基盤である住居はそのままに、借金問題を解決できるのです。この点は、給与所得者等再生の最大の魅力といえるでしょう。家族の生活基盤を維持したまま、債務整理を進めることができます。
「毎月の住宅ローン返済に追われながら、他の借金返済にも苦しむ」という状況から抜け出す道があるのをご存知でしょうか。 債務整理の一つに、借金を大幅に減額してくれる個人再生という手続きがあります。その個人再生にある住宅ローン特則と呼ばれる[…]
給与所得者等再生のメリットとデメリット
給与所得者等再生の大きな利点は、前述の住宅維持に加え、借金の一部免除を受けられることです。具体的には、クレジットカード債務やキャッシング等の住宅ローン以外の借入金について、定められた返済計画に従って債務の一部が免除されます。
一方で、返済計画については、自分の希望が通りにくいというデメリットがあります。3年以内という返済期間の制限があり、毎月の返済額も、収入に応じて一定の計算式で自動的に算出されてしまいます。そのため、収入が不安定な人には向かない制度といえるでしょう。
\LINEで気軽に相談可能!/
給与所得者等再生の要件と必要書類

制度を利用するには、満たすべき要件があります。給与所得者等再生を利用するなら、自身の状況が条件に合致するか、しっかり確認しておきましょう。
安定した収入があること
給与所得者等再生の最重要条件は、安定した給与収入があることです。ここでは、会社員やパート、アルバイトの方などが対象となります。収入が不安定であったり、一定額の返済能力がない場合は適用されません。
収入証明書の提出は必須です。会社からもらう源泉徴収票や給与明細書など、安定した収入を証明できる書類が求められます。
裁判所の審査では、毎月の収入から生活費等を差し引いた金額をベースに、返済可能額が算出されます。事前に立てた返済計画が本当に実行できるのか、審査時に重視される点は押さえておきましょう。
借金総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下であること
給与所得者等再生を利用するためには、住宅ローンを除いた借金総額が5000万円を超えてはいけません。この制度は、比較的少額の債務を抱える給与所得者の生活再建を支援することを目的としているからです。
借金の総額を確認する際は、債権者からの残高証明書や返済予定表などの書類が必要となります。また、住宅ローン以外のすべての借入金(クレジットカードやキャッシング、消費者金融からの借入など)を合算した金額が対象となります。
過去7年以内に、自己破産や給与所得者等再生、ハードシップ免責を行なっていないこと
給与所得者等再生のその他の条件として、過去7年以内に他の債務整理手続きを行っていないという条件があります。これは、制度の適切な運用と債務者の誠実性を確保するためです。
過去の債務整理歴は裁判所で厳密にチェックされます。この要件を満たさない場合、申し立てが却下される可能性が高いため、事前によく確認することが大切です。
また、予期せぬ事情により再生計画通りに返済できなくなった場合、4分の3以上の返済を行っていれば、残りの支払義務が免除される「ハードシップ免責」という制度も対象です。
この免責を受けた場合も、新たな給与所得者等再生の申し立てには7年の経過が必要となります。この要件は、債務整理制度の安定性を保ち、真に支援を必要とする方々への適切な手助けを確保することを目的としています。
必要な手続きと書類
申立書類の準備では、収入証明書や資産状況を示す書類が必要となります。財産目録や債権者一覧表など、複数の書類を揃えておきましょう。
なお、原則として、収入証明書は会社から貰い受けたものを提出します。源泉徴収票のほか、直近の給与明細書なども求められるケースがありますが、会社が発行したものであれば基本的に問題ありません。
返済計画書は、債務整理の核となる大切な書類です。収入や生活費を考慮した上で、無理のない返済プランを立てていきます。制度利用の成否に関わるため、専門家のアドバイスを受けながら作成すると良いでしょう。
\LINEで気軽に相談可能!/
小規模個人再生との違い

債務整理手続きにおいて、「給与所得者等再生」と「小規模個人再生」は、一見共通点があるように見えます。
しかし、大きな違いがいくつもあり、誤った制度を選んでしまうと深刻な事態を引き起こす可能性も。両制度の特徴と違いを正確に理解し、解決の糸口を探していきましょう。
給与所得者等再生と小規模個人再生の違い
給与所得者等再生と小規模個人再生は返済計画の柔軟性が大きく異なります。
小規模個人再生では返済額を借金総額の5分の1程度まで抑制できます。一方で給与所得者等再生は毎月の返済額が「給料から標準的な生活費を引いた残り」とされ、柔軟性に欠けています。返済期間も原則3年以内と定められており、収入に応じた返済が求められます。
小規模個人再生は自営業者でも利用できます。収入が不規則でも制度を利用できる点が特徴です。いわば、給与所得者等再生の「縛り」を緩和した制度と言えるでしょう。
ただし、柔軟性と引き換えに、債権者の同意を得にくい側面もあります。給与所得者等再生と違い、返済計画が否決されるリスクも考慮に入れる必要があるでしょう。
裁判所も小規模個人再生の申立人に対し、返済計画の実現可能性を慎重に審査します。返済能力の証明は給与所得者等再生より厳格になる傾向にあります。
選び方のポイント
どちらの制度が自分に適しているか、最も簡単な判断基準は、安定した収入があるかどうかです。サラリーマンやパート、アルバイトの方で毎月の給与収入が見込める場合、手続きが簡単な給与所得者等再生がおすすめです。
逆に、収入が不安定であったり、事業収入がメインの場合は、小規模個人再生が向いています。生活状況に応じているかどうかも含めて、どの制度を利用するか決める必要があります。
住宅ローンを抱えている場合は、住宅ローン特則のある給与所得者等再生が有利です。また、扶養家族の有無や教育費など、将来的な支出見込み、収入増減の可能性なども総合的に判断しなくてはいけません。
給与所得者等再生を利用するのか、小規模個人再生を利用するのか、債務整理の成否を左右する重要な判断となるため、専門家への相談を強くおすすめします。
\LINEで気軽に相談可能!/
まとめ

給与所得者等再生と小規模個人再生のどちらの制度も、借金問題を解決するための大切な選択肢です。
給与所得者等再生は手続きが簡素で住宅を維持しやすい一方、返済期間の制限があります。小規模個人再生は柔軟性が高いものの、債権者との話し合いが必要で、手続きが複雑です。
債務整理には専門的な知識と経験が必要です。当事務所では借金問題に関する相談を随時受け付けています。一人で悩まず、まずは専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
借金返済にお困りなら今すぐご相談ください
当事務所は任意整理・個人再生・自己破産に対応しています(司法書士業務の範囲内に限る)。どの手続きが良いか分からない場合、ご依頼者様の状況を見てご提案しますのでご安心ください。
当事務所は任意整理・個人再生・自己破産に対応しています(司法書士業務の範囲内に限る)。どの手続きが良いか分からない場合、ご依頼者様の状況を見てご提案しますのでご安心ください。