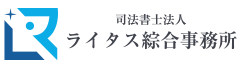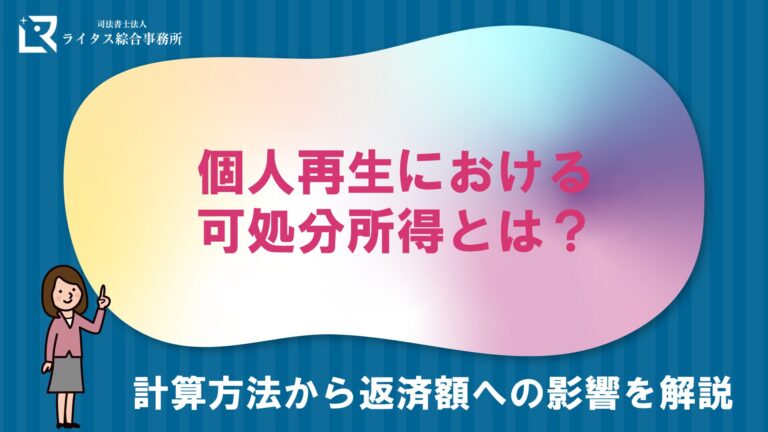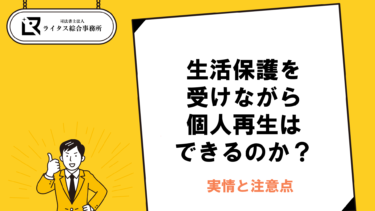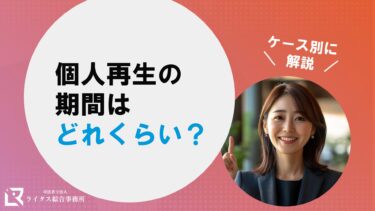個人再生を検討中の方にとって、「可処分所得」という言葉はあまり聞き慣れないかもしれません。しかし、給与所得者等再生という手続きを選ぶ場合、この可処分所得が返済額を左右する重要な要素となります。
今回は、可処分所得の意味や計算方法、返済額との関係までを詳しく解説します。正しい知識を得ることで、自分に合った債務整理の手続きを選ぶ助けになるはずです。
個人再生における可処分所得とは

給与所得者等再生を選択する際に、重要となるのが可処分所得です。返済可能額を算出するために不可欠な指標であり、この数値が弁済額の最低ラインを決める根拠となります。
この概念をしっかり理解することで、手続き全体の仕組みや目的も見えてきます。
可処分所得の定義
個人再生における可処分所得とは、収入から税金や社会保険料、最低生活費を差し引いた自由に使える金額のことです。実質的には、債務返済に充てられる金額を意味します。
総務省統計局では「実収入から非消費支出を控除した手取り収入」と定義されますが、個人再生では異なる算出方法が採用されており、独自の基準が用いられています。
給与所得者等再生においての計算式は「(収入-税金-社会保険料)-政令基準の生活費」です。政令基準の生活費は、生活保護の基準を参考に設定されており、地域や家族構成によって金額が変動します。
個人再生において可処分所得が重視される理由
給与所得者等再生の弁済額は、「最低弁済基準」「清算価値」「可処分所得2年分」のうち、最も高い金額が基準になります。
小規模個人再生とは異なり、債権者の同意を得る必要がない代わりに、返済能力を具体的な数値で明示しなければなりません。可処分所得を基準とすることで、債務者の返済能力が客観的に評価されます。
なお、生活費の基準が地域ごとに異なるため、同じ収入でも可処分所得に差が生じる場合があるため注意が必要です。例えば、東京23区と地方都市では生活費に大きな違いがあるため、結果として返済額に影響を及ぼすケースもあります。
可処分所得の考慮が必要となる「給与所得者等再生」の特徴
この手続きは、会社員や公務員など、安定した収入がある給与所得者が対象です。自営業者や個人事業主などは原則として対象外です。
小規模個人再生と違い、債権者の過半数が反対した場合でも手続きを進められる反面、可処分所得の2年分以上の返済という条件が課されます。そのため、人によっては返済額が高くなる可能性があります。
また、住宅ローン特則を利用することで、自宅を維持したまま借金問題を解決できる点が特徴です。マイホームを手放したくない方にとっては、魅力的な選択肢です。
借金問題でお困りの方のために、法的な解決手段としてまず「個人再生」という制度があります。その中でも、生活再建を実現する制度として「給与所得者等再生」と「小規模個人再生」というものが存在します。 両制度は、利用できる条件や手続きの流れに[…]
\LINEで気軽に相談可能!/
可処分所得の計算方法
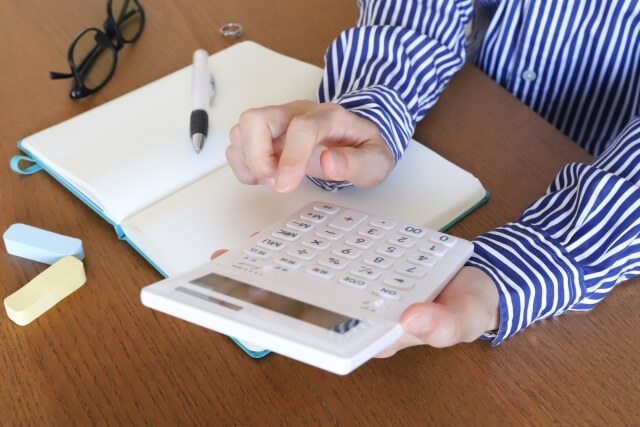
正確な可処分所得を算出するには、収入や支出の内容を詳細に把握しておく必要があります。書類の準備から地域区分の確認まで、多くの段階があります。
間違った計算をしてしまうと、想定外の返済額になってしまう可能性があるため、慎重に進めましょう。
収入・支出の具体的な項目と記載方法
必要書類としては、過去2年分の源泉徴収票と課税証明書、住民票などがあります。収入には、給与だけでなく、賞与や各種手当も含まれるため、年収の総額を正しく把握することが大切です。
控除対象には、所得税・住民税・社会保険料のほか、政令基準に基づいた生活費(家賃・光熱費などを含む)があります。特別な事情がある場合は、医療費など個別に考慮されることもあります。
「可処分所得額算出シート」を使って計算し、居住地に応じて1区から6区に分けられた生活費基準を適用しなければなりません。
可処分所得の年間計算
計算式は以下が基本となります。
年間の可処分所得を算出し、それを2倍した金額が弁済額の基準です。転職や昇進、残業時間の変化などで、収入が5分の1以上変動した場合は、月収ベースで再計算が必要です。
また、住宅ローンや医療費など特別な支出がある場合は、個別に考慮される可能性があります。ただし、自動的に控除されるわけではないため、必要に応じて裁判所や専門家に相談することが大切です。
家計の状況が可処分所得に与える影響
家族の人数が増えると、その分認められる生活費も増え、可処分所得は減少します。配偶者や子供、高齢の親を扶養している場合、それぞれに生活費が加算されるため、返済額を抑えられる場合もあります。
また、居住地域によって生活費の基準に差がある点にも注意が必要です。第1区の東京23区と地方の第4〜6区では生活費に大きな差があり、最低生活費の基準額に相当な開きが生じることもあります。
さらに、住居形態によっても扱いが異なります。賃貸住宅では実際の家賃が考慮されますが、持ち家の場合は住宅ローン返済中なら実際の返済額が、住宅ローンがなければ状況に応じて政令基準額または0円が適用される仕組みです。
\LINEで気軽に相談可能!/
可処分所得が返済額に与える影響
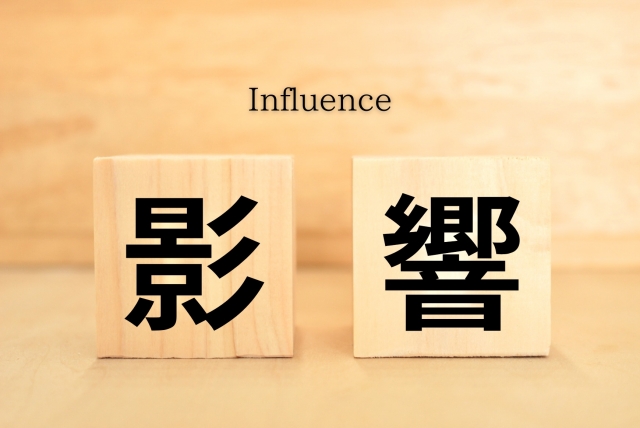
可処分所得は、最終的な返済額を決定する重要な要素の一つです。他の基準との比較により、実際に支払う金額が決まるため、その仕組みと影響を理解しておくことが欠かせません。
可処分所得の仕組みを把握しておくことで、将来の返済計画を立てやすくなります。
最低弁済額の決まり方と計算根拠
個人再生における最低弁済額は、債務総額に応じ5段階に分類され、金額が定められています。
給与所得者等再生では、最低弁済基準と清算価値、可処分所得2年分の3つのうち、最も高い金額が返済額として採用されます。
つまり、たとえ債務総額に基づく最低基準が比較的低かったとしても、可処分所得が高く計算された場合には、その金額が返済額の下限となることがあるので、注意が必要です。
可処分所得が高い場合の注意点
収入が増えると、可処分所得も上がり、結果として弁済額が想定よりも高くなる場合があります。昇進や転職による年収アップは、思わぬ負担増につながることもあるため注意が必要です。
また、収入の増減が5分の1以上あった場合、再計算しなければならず、弁済額が変わる可能性があります。計算上は返済できる金額であっても、実際の生活では困難なこともあります。そのため、現実的な収支管理と生活設計が欠かせません。
不安な場合は専門家のサポートを受けよう
司法書士や弁護士に相談すれば、算出シートの作成から生活費基準の確認まで幅広くサポートを受けられます。経験豊富な専門家に依頼することで、誤った計算や不利な条件を回避できる可能性があります。
また、将来的な収入変動を見越した返済計画についても相談できるため、安心して手続きを進めるための一助となるでしょう。
個人再生は、多重債務者が借金の減額や返済計画の見直しを行うための法的手続きですが、その際に専門家のサポートが必要です。弁護士と司法書士は個人再生の手続きをサポートする役割を担っていますが、依頼する際にどちらを選ぶべきか迷うこともあるでしょう[…]
\LINEで気軽に相談可能!/
まとめ

給与所得者等再生において、可処分所得は返済額を左右する非常に重要な指標です。生活費や税金、地域区分といった複数の要素によって変動するため、正確な理解と計算が求められます。
不安がある場合は、専門家に相談しながら手続きを進めることで、無理のない返済計画を立てられるでしょう。当事務所でも相談を随時受け付けていますので、一人で悩まず、ぜひお気軽にご相談ください。
借金返済にお困りなら今すぐご相談ください
当事務所は任意整理・個人再生・自己破産に対応しています(司法書士業務の範囲内に限る)。どの手続きが良いか分からない場合、ご依頼者様の状況を見てご提案しますのでご安心ください。
当事務所は任意整理・個人再生・自己破産に対応しています(司法書士業務の範囲内に限る)。どの手続きが良いか分からない場合、ご依頼者様の状況を見てご提案しますのでご安心ください。