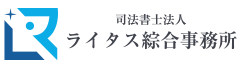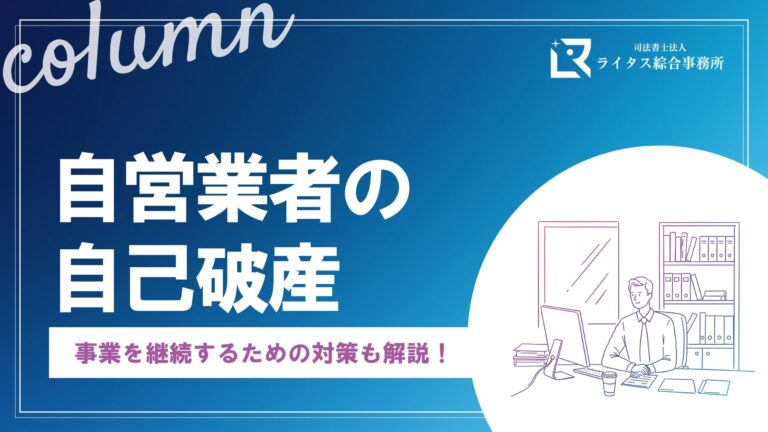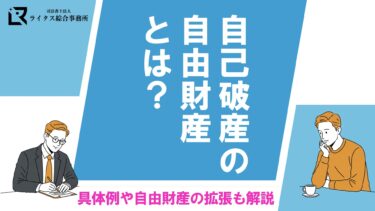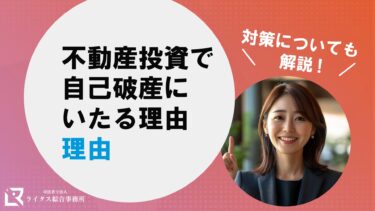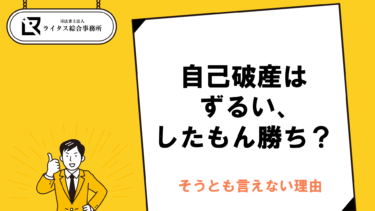借金の返済が難しくなり、自己破産を検討している自営業者の方は多いでしょう。自営業者が自己破産する場合「事業を続けられなくなるのでは」と不安を抱える方が多いです。
実際に、自己破産すると事業用の財産が処分対象になり、事業継続が難しくなるケースが少なくありません。
しかし、自己破産後も事業を続ける方法は存在します。債務整理の中でも最も強力な手段である自己破産ですが、事前に知識をつけておけば、事業の再スタートを切ることも可能です。
本記事では、自営業者が自己破産する場合の流れや費用、影響、そして事業継続のための対策について詳しく解説します。また、売掛金の扱いについても触れていますので、借金問題で悩む自営業者の方は、ぜひ参考にしてください。
自営業者が自己破産する場合の流れ、費用、影響
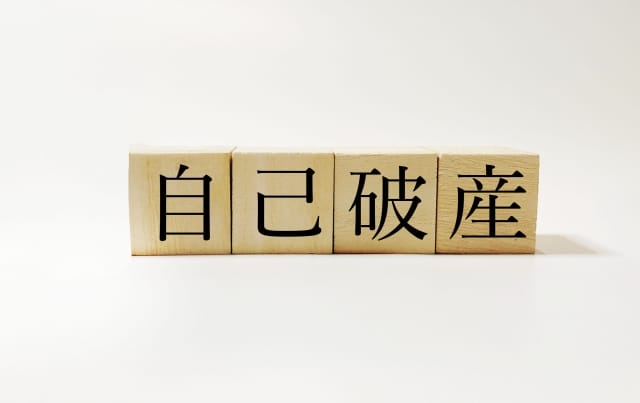
自営業者が自己破産をする場合、サラリーマンとは異なる手続きや影響があります。まずは、自営業者の自己破産の基本的な流れや特徴を理解しましょう。
自営業者の自己破産の流れ
自己破産の手続きには、同時廃止、管財事件、少額管財の3種類があります。自営業者は、この3種類の中で、通常は管財事件が適用されます。事業規模が小さい場合は、少額管財が適用されます。
管財事件とは、事業に関連する財産や負債を含むため、裁判所が管財人を選び、財産の処分や負債の整理を行う手続きです。具体的には、破産申立書の作成から始まり、裁判所による破産手続開始決定、債権者集会の開催、免責許可の決定という流れをとります。
サラリーマンの場合は、比較的短期間で終わる同時廃止が適用されることが多いです。対して自営業者の場合は、管財事件となるため手続き期間が長くなる傾向があります。
自営業者の自己破産の費用
自己破産の費用には、弁護士費用や手続き関連の費用が含まれます。弁護士費用は、手続きの種類によって異なり、管財事件の場合は30万円から80万円程度です。
その他の費用としては、申立手数料や官報公告費用(総じて予納金)などがあります。申立手数料は裁判所に支払う費用のことです。
費用は法律事務所によって異なるため、事前に見積もりを取りましょう。多くの法律事務所では、分割払いにも対応しています。自己破産をするときに、経済的に苦しい状況でも相談することが可能です。
また、法テラスの民事法律扶助制度を利用すれば、立替払い制度を利用できる場合もあります。費用面で不安がある方は、一度法テラスに問い合わせてみるとよいでしょう。
自営業者が自己破産する場合の影響
自己破産をすると、事業に必要な設備や在庫が処分される可能性があり、事業の継続が難しくなります。事業用の財産は借金返済のための資源として扱われるため、処分の対象です。
さらに、個人の生活にも影響を及ぼします。個人で所有している車や高級品などが処分されることがあります。ただし、日常生活に必要な家財道具や99万円以下の現金は「自由財産」として手元に残すことが可能です。
また、自己破産すると取引先との信用が失われることもあり、再び融資を受けることが難しくなるでしょう。
自己破産の情報は5年から10年の間、信用情報機関に登録されます。自己破産の記録が残っている間にローンやクレジットカードを使えないことで、事業を継続するための資金繰りが厳しくなる可能性が高いです。
\LINEで気軽に相談可能!/
自営業者が自己破産後も事業を継続するための対策
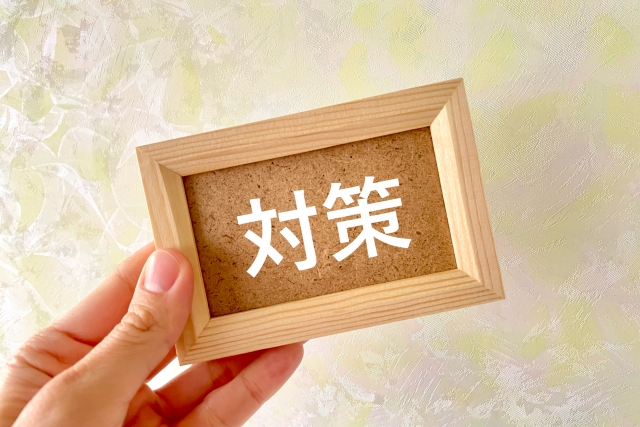
自営業者が自己破産をしても、事業を継続する方法はあります。次の項目では、自営業者が自己破産後も事業を続けるための対策について解説します。
自由財産の拡張の申請をする
自己破産でも「自由財産」として、一定の財産を手元に残すことができます。自由財産には99万円以下の現金などが含まれますが、事業用の設備は通常含まれません。しかし、自由財産の拡張が認められれば、事業用の財産を手元に残せる可能性があります。
自由財産の拡張を認められれば、生計を立てるために必要な道具や機械などを自由財産として認めてもらえるケースがあります。自由財産の拡張を求めるときは、裁判所に申請を行い、財産が生活再建に必要であることを証明する資料を提出する必要があります。
とくに小規模な個人事業主の場合、使用している工具や機材が生活維持に不可欠であると認められやすく、自由財産の拡張が認められる可能性が高まります。
他の債務整理を検討する
自己破産以外の債務整理として、任意整理や個人再生が考えられます。任意整理や個人再生は、自己破産ほど厳しい条件ではないため、事業を継続しながら負債を整理する手段として利用できるでしょう。
任意整理では、債権者と交渉して返済条件を緩和することが可能です。利息のカット、元金の分割払いなどを交渉し、毎月の返済負担を軽減できます。
個人再生は、個人事業主でも利用できる債務整理手続きです。個人再生は、債務を最大で10分の1まで圧縮し、3〜5年かけて返済していきます。
個人再生の大きなメリットは、自己破産と違って事業用財産を処分せずに済む点です。事業を継続しながら債務整理ができるため、自営業者にとってメリットが大きい選択肢となるでしょう。
借金が返せなくなり、不安な日々を送っていませんか?そんな時は、債務整理という方法があります。 債務整理には、様々な方法がありますが、どの方法を選ぶべきかは、借金の額や収入、財産状況などによって異なります。 この記事では、債務整理[…]
事業の立て直し
自己破産後も事業を継続するためには、事業の立て直しが重要です。新たなビジネスモデルやマーケティング戦略を考える必要があるでしょう。収益を増やすための仕組みの見直しや、経費削減を図り、持続可能な事業運営を目指しましょう。無理に事業を拡大するよりも、堅実な経営を心がけることが大切です。
また、取引先との信頼関係を再構築することも大切です。自己破産により信用が低下している状態で、新たな信頼関係を築くのは簡単ではありません。しかし、誠実な対応と確実な納品・サービス提供を続けることで、徐々に信頼を回復することができるでしょう。
事業の立て直しには、専門家のアドバイスを得ることも有効です。公認会計士や税理士、中小企業診断士などの専門家に相談することで、効果的な経営戦略を立てることができます。
\LINEで気軽に相談可能!/
自己破産における売掛金の扱い

自営業者にとって、売掛金は重要な財産です。次の項目では、自己破産時の売掛金の扱いについて詳しく解説します。
売掛金の回収時期でどのように変わるか
自己破産の手続きを開始した段階で、すでに受け取っている売掛金は、他の財産と同様に裁判所に回収されます。これは、破産手続き開始時点で破産者が保有している財産は全て破産財団に組み込まれるためです。
まだ受け取っていない売掛金は、破産管財人が取引先から直接回収します。破産手続き開始決定後は、破産者自身が売掛金を回収することはできなくなります。
破産手続き開始後に発生した売掛金は「新得財産」といって、手続きの中で没収される心配はありません。破産手続き開始後の労働や事業活動によって得た収入は、原則として破産者のものとなります。
売掛金が自由財産として認められる条件
売掛金は通常、自由財産として認められません。ただし、例外的に売掛金が自由財産として認められることがあります。売掛金を自由財産として認められるケースは、対象の売掛金が生活費に充てられる予定であったり、事業再建のために不可欠であったりする場合です。
売掛金を自由財産として認めてもらうためには、99万円枠の審査をクリアする必要があります。売掛金を99万円以内に収めることができれば、自由財産として認められる可能性が高まるでしょう。
自己破産は借金問題を解決する一つの手段ですが、「全ての財産を失ってしまう」というイメージを持つ方も多いでしょう。 しかし実際には、債務者の生活再建のために一定の財産が保護される「自由財産」という制度があります。自由財産制度によって、最[…]
売掛金が給料と同様に扱われるケース
フリーランスや一人親方の売掛金は、実質的に給料と変わらない場合もあります。このような場合、売掛金は全額ではなく4分の1のみが没収の対象となり、残りは破産者が受け取ることができます。
売掛金が生活の維持に必要な場合には、売掛金を手元に残すことが可能です。とくに、継続的な取引先からの売掛金で生計を立てている場合は、給与と同様の扱いを求めることができます。
ただし、具体的な取り扱いは個別の状況によって異なります。売掛金の額や性質、破産者の生活状況などを総合的に判断して決定されるため、売掛金の扱いに困った場合は、専門家に相談するようにしましょう。
\LINEで気軽に相談可能!/
まとめ

自己破産は、自営業者にとって大きな影響を与える手続きです。しかし、自由財産の拡張や他の債務整理を利用することで、事業を立て直せる可能性があります。
自己破産を検討する際は、まず専門家に相談し、自分の状況に最適な債務整理方法を選ぶことが重要です。当事務所では、自営業者の自己破産に関する相談も随時受け付けています。まずは一人で悩まずに専門家に相談されてみてはいかがでしょうか。
借金返済にお困りなら今すぐご相談ください
当事務所は任意整理・個人再生・自己破産に対応しています(司法書士業務の範囲内に限る)。どの手続きが良いか分からない場合、ご依頼者様の状況を見てご提案しますのでご安心ください。
当事務所は任意整理・個人再生・自己破産に対応しています(司法書士業務の範囲内に限る)。どの手続きが良いか分からない場合、ご依頼者様の状況を見てご提案しますのでご安心ください。