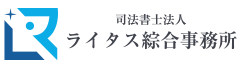債務整理について
- CICは完済から5年でどうなりますか?
CICに登録された事故情報(ブラックリスト)は、基本的に借金完済から5年経過後に自動的に削除されます。ただし、本人宛に通知などがされるわけではないため、ご自身の目で確認するにはCICへの「信用情報開示請求」を行う必要があります。
もし、完済から5年以上が経過しているにも関わらず事故情報が削除されていなかった場合は、CICに対して削除請求を行いましょう。司法書士法人ライタス綜合事務所では、削除請求のサポートも可能です。
- アコムの一括請求が払えません。どうしたらいいですか?
アコムに限らず、一括請求に対応できない場合、まずはアコム総合カードローンデスク(0120-629-215)へ連絡を取り、返済に関する相談をしてみましょう。 多くの場合、猶予期間をもらうことができます。
それでも返済困難な場合は、司法書士法人ライタス綜合事務所にご相談ください。債務整理を行うことで一括請求を一時的に保留し、借金問題の解決に向けた手続きを進めることができます。
- アコムの借金は何年で消えますか?
アコムに限らず、消費者金融や銀行などからの借金の時効期間は、最後の取引日から5年間です。ただし、以下の条件で時効が更新されるため注意が必要です。
・裁判で敗訴判決が確定した場合は確定日から10年間
・一部返済や支払い約束をすると期間がリセットされ5年間
つまり、時効成立には最後の取引日から5年以上の経過、その期間に一部返済や支払い約束(債務承認)がないこと、裁判未提起が条件という厳しいものとなっています。
- アコムの任意整理は何年で完済できますか?
アコムに限らず、任意整理では平均3~5年(36〜60回払い)の返済期間が設定されます。基本的に、5年以上の分割返済には応じてもらえないケースが多いです。
もし、任意整理をしても完済までに5年以上を要することが想定される場合は、個人再生や自己破産といった、別の債務整理手続きによる解決が適しています。
- 個人再生は履歴が何年で消えますか?
個人情報機関によって異なりますが、基本的には完済から5~7年程度で、個人再生による事故情報は削除されます。
ただし、事故情報が削除されても通知はされないため、ご自身で各信用情報機関に確認する必要があります。
司法書士法人ライタス綜合事務所では、各信用情報機関への「信用情報開示請求」のサポートが可能です。
- 個人再生でやってはいけないことは?
個人再生では以下のような行為が禁止されています。
・裁判所への虚偽の申告
・裁判所や個人再生委員の指示に従わない
・再生計画案を期限内に提出しない
・履行テストの不履行
・新たな借入や浪費行為
・手続費用の未納付
・偏頗弁済(特定の債権者にのみ返済する行為)
上記の禁止事項を守らない場合、裁判所から個人再生の棄却や廃止、不認可とされるおそれがあるため注意しましょう。
- 個人再生で何を調べられますか?
個人再生では財産状況について、以下3つの観点から調査が実施されます。
・財産調査
預貯金、給与・退職金、不動産、車両、生命保険の解約返戻金、有価証券、仮想通貨、積立金などの保有状況について
・不正調査
財産隠し、特定債権者への偏頗弁済、詐害行為(意図して事故の財産を減少させる行為)などについて
・債権調査
債権者が保有している正確な債権額、再生手続から漏れている債権者について
- 個人再生で嫁の通帳は必要ですか?
個人再生では、基本的に配偶者の通帳まで提出を求められることはありません。ただし、以下のような状況下では、裁判所に配偶者の通帳が必要と判断されることがあります。
・配偶者名義の借金を夫が支払っている場合
・本人の通帳から配偶者宛に多額の送金がされている場合
・水道光熱費など生活費に関連する引き落としが配偶者名義の口座である場合
・一定の収入がある場合
条件に当てはまらず通帳の提出を求められなくても、非課税証明が必要になることがあります。
- 個人再生で借金はどれくらい減る?
個人再生による最低弁済額は、借金総額により決定されます。
・100万円未満は減額なし
・100万円以上500万円以下は100万円
・500万円以上1,500万円以下は総額の5分の1
・1,500万円以上3,000万円以下は300万円
・3,000万円以上5,000万円以下は総額の10分の1
ただし、「清算価値保証の原則」といって、保有財産の価値(清算価値)を下回る減額は認められていません。清算価値が最低弁済額を上回る場合は、清算価値と同額が個人再生の返済額になります。
- 個人再生にかかる費用はいくらですか?
個人再生にかかる一般的な費用相場の内訳は以下の通りです。
・裁判所の費用 3万円~30万円
・弁護士や司法書士の費用 30万円~50万円
裁判所費用には収入印紙代(1万円程度)、郵便切手代(2,000円~5,000円程度)、官報公告費用(12,000円~14,000円程度)が含まれます。
なお、個人再生委員が選任される場合は別途20万円~25万円程度が必要です。
司法書士法人ライタス綜合事務所における個人再生の費用は、着手金125,000円~、報酬金125,000円~です。住宅ローン条項付の場合は、別途60,000円が加算されます。
- 個人再生になると携帯はどうなりますか?
個人再生をしても、基本的に携帯電話は現状どおり使用可能です。
ただし、通信料金や端末代金の滞納がある場合、契約が解約されてしまうおそれがあります。
とはいえ、解約されてしまったとしても、他の携帯会社や格安SIM、プリペイドスマホへの切り替えで携帯電話自体は利用継続できるのでご安心ください。
- 個人再生に失敗したらどうなる?
個人再生に失敗した場合、借金が減額されることはありません。また、手続き中に発生した遅延損害金や利息が加算されて請求されることになります。
とはいえ、個人再生に利用回数などは設定されていないため、失敗した原因を分析した上で、再度申し立てることが可能です。ただし、返済能力を理由に個人再生が失敗していた場合は、自己破産への移行も視野に入れなければなりません。
- 個人再生の最低収入はいくらですか?
個人再生には最低収入額の定めはありません。
ただし、「将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること」が利用条件となっています。個人再生による返済額は借金総額にもよるため一概に言えませんが、手続きの中で減額された借金を3年間(最長5年間)で返済していけるだけの資力があれば、個人再生を完遂させることが可能です。
- 個人再生の成功率は?
令和5年度の司法統計データによると、利用者の多い小規模個人再生では92.47%、給与所得者等再生では89.57%の手続きが完了しており、再生事件全体では92.21%の方が手続きを完了しています。
過去のデータを見ても成功率はおおむね安定しており、個人再生の成功率は約92%、手続きが失敗するケースは約8%にとどまります。
この背景には、個人再生手続きの多くが司法書士といった専門家のサポートを受けながら進められるため、成功率が高い傾向にあることが挙げられます。
- 個人再生は、何歳までできますか?
個人再生に年齢制限はありません。
たとえ高齢者であっても、収入のある方であれば利用可能です。ただし、個人再生は3~5年の間に減額された借金の完済を目指す手続きです。収入が年金のみの方や、働けない理由のある方が利用するのは困難といえます。
- 個人再生はずるいですか?
個人再生は決してずるい制度ではありません。返済不能に陥ってしまいそうな債務者の経済的再生を支援する目的で、国が創設した制度です。また、個人再生は裁判所が関与し、手続きの妥当性を判断した上で、借金が減額される仕組みになっています。手続きの中で債権者への配慮もしっかりされているため、安心してご利用ください。
どうしても心配な方は、司法書士法人ライタス綜合事務所にご相談ください。
- 個人再生は妻に影響しますか?
個人再生は、配偶者に対して直接的な影響を及ぼす手続きではありません。
ただし、配偶者が借金の保証人になっている場合、個人再生による減額分を超えた金額については、保証人である配偶者に請求されるため注意が必要です。状況によっては、夫婦揃っての個人再生や、別の債務整理手続きの利用を検討しなければなりません。
その他にも、裁判所の判断で配偶者の収入を証明する資料を提出する必要があり、再生計画の履行において配偶者の収入が考慮される場合があります。
- 個人再生は職場にバレますか?
職場が債権者の場合を除き、個人再生の通知が職場に届くことはなく、原則としてバレる心配はありません。ただし、手続きの中で「退職金見込額証明書」の発行を依頼する場合は、個人再生の事実が判明する可能性があります。
また、個人再生をすると官報にその事実が掲載されますが、一般企業が定期的に官報をチェックすることは稀なので、それほど心配する必要はありません。仮に職場に個人再生がバレたとしても、その事実だけを理由に解雇はできないのでご安心ください。
- 個人再生をしたら口座がバレる?
個人再生は、裁判所に申立前1〜2年分の預金通帳を提出する必要があります。
その他に、財産目録や直近2~3ヶ月分の家計簿、給与明細などの提出も求められ、不自然な資金移動は即座に発覚するため注意してください。
また、口座を意図して隠蔽すると個人再生が認められず、借金問題を解決できない自体に陥ってしまうリスクがあるため、口座情報は必ず提出しましょう。
- 個人再生をしたら税金はどうなりますか?
個人再生をしても、税金の支払義務が免除されることはありません。税金の滞納があるのであれば、借金の支払いよりも優先して支払いましょう。
なお、税金を滞納していると、預金口座や給与の差押えをされる危険があり、個人再生の手続きに支障が生じるおそれもあります。手続き開始前に滞納分の分納を認めてもらうなど、税務署や自治体と十分な協議をしてから申立準備をはじめてください。
- 個人再生中にギャンブルをしたらバレますか?
個人再生では、裁判所や個人再生委員の調査が入りますが、ギャンブルをしているかまで確認する術はありません。
しかし、ギャンブルが理由となり、裁判所に提出する家計収支表や通帳の記載に矛盾が生じるおそれがあるため、やらないに越したことはありません。仮にギャンブルが発覚した場合、裁判官の心証を損ねてしまい、手続きに失敗する可能性が高くなります。「ギャンブルをやめられるか不安」「個人再生の手続きが心配」という方は、司法書士法人ライタス綜合事務所へご相談ください。
- 個人再生中に禁止されていることは何ですか?
個人再生では以下のような行為が禁止されています。
・裁判所への虚偽の申告
・裁判所や個人再生委員の指示に従わない
・再生計画案を期限内に提出しない
・履行テストの不履行
・新たな借入や浪費行為
・手続費用の未納付
・偏頗弁済(特定の債権者にのみ返済する行為)
上記の禁止事項を守らない場合、裁判所から個人再生の棄却や廃止、不認可とされるおそれがあるため注意しましょう。
- 債務整理したら携帯は買えないの?
債務整理をしても携帯電話を購入することは可能です。
ただし、債務整理をすると信用情報機関に事故情報が登録されてしまいます。いわゆる「ブラックリスト」という状態になるため、携帯電話本体の割賦契約(分割払い)が難しくなります。とはいえ、一括払いであれば購入することはできますし、家族名義での契約、中古の機種を購入するなど、私生活への支障はほとんどないのでご安心ください。
- 債務整理で2ヶ月滞納したらどうなる?
司法書士に債務整理を依頼すると、その時点で債権者への返済は一旦ストップします。 ただし、契約内容によっては、2ヶ月程度の滞納でも問題が生じる可能性があるため、注意が必要です。
また、司法書士が介入していても、和解の成立や裁判所への申立てまでに時間がかかることがあります。 その間に債権者から訴訟を起こされる可能性もあるため、手続きをスムーズに進めるためにも、早めに相談することが大切です。
依頼後は一時的に返済が止まりますが、いずれ再開されるため、備えて資金を確保しておくことをおすすめします。 ただし、各ケースに応じた慎重な対応が必要です。
- 債務整理で払えなくなったらどうなる?
債務整理で返済が必要になる手続きには、「任意整理」と「個人再生」があります。 どちらの手続きでも、返済が難しくなった場合は、すぐに担当の専門家へ相談することが重要です。
なぜなら、返済が長期間ストップすると、債権者から裁判を起こされる可能性があるためです。 最悪の場合、銀行口座や不動産、給与の差し押さえに発展する危険性もあります。
もし、債務整理担当だった専門家との受任関係が途切れている場合は、司法書士法人ライタス綜合事務所へのご相談もご検討ください。それぞれの状況に応じた適切なアドバイスをさせていただきます。
- 債務整理にかかる費用は?
債務整理費用は、依頼する事務所、手続きの種類によって異なります。
司法書士法人ライタス綜合事務所では、以下の料金となります。
・任意整理 基本報酬(着手金込み)1社/44,000円+減額した額の11%
・個人再生 着手金125,000円~、報酬金125,000円、住宅ローン条項付き60,000円加算
・自己破産 着手金110,000円~、報酬金110,000円~
なお、すべて税込み価格、着手金は後払い・分割払いでの対応が可能となっています。
- 債務整理のデメリットは?
債務整理は手続きごとに異なるデメリットがあります。
債務整理共通のデメリットは、信用情報機関に事故情報が登録され(ブラックリスト)、5〜7年間は、クレジットカード作成・利用、住宅ローン等の新規借入、携帯電話の分割払い等が困難になってしまう点です。裁判所での手続きとなる個人再生、自己破産では、住所や氏名が官報に掲載される点がデメリットです。また、自己破産では一部の資格や職業が手続き中のみ制限されるデメリットがあります。
- 債務整理は何年で終わる?
債務整理は手続きによって所要期間が異なります。
一般的に、任意整理は3~6ヶ月程度、返済期間が3~5年です。個人再生は手続き期間が6ヶ月~1年、返済期間が原則3年、特別な事情があれば5年です。自己破産は、手続き期間が6ヶ月~1年程度で、手続き終了と同時に返済義務がなくなります。
- 債務整理は電話だけで依頼できますか?
債務整理は原則として電話だけで依頼することはできません。
日本司法書士連合会では、債務整理を受任する際は個別面談による事情聴取を義務付けています。ただし、特別な事情がある場合や、依頼の前段階としての相談であれば、電話での対応も可能です。
司法書士法人ライタス綜合事務所では、オンラインでの電子契約(クラウドサイン)も導入しております。どうぞお気軽にご相談ください。
- 債務整理をしたら会社にバレますか?
債務整理をしても会社にバレることは基本的にありません。
ただし、会社からの借入がある場合など、会社が債権者になっている場合は、司法書士や裁判所からの通知を防ぐことはできません。 どうしても会社に知られたくない場合は、任意整理を選択し、手続きの対象から会社を外すことで回避できます。
また、自己破産には一部の資格・職業に制限があるため、会社が債権者でなくても、制限対象の職業に就いている場合は、会社への申告が必要となることがあります。
- 債務整理をしたら会社をクビになりますか?
債務整理をしても会社をクビになることはありません。
債務整理を理由とした解雇は禁止されています。会社は債務整理や借金の事実だけを理由に従業員を解雇することはできません。ただし、自己破産の場合のみ、弁護士、税理士、警備員、生命保険外交員など一部の資格・職業に制限がかかるため注意が必要です。クビになる心配はないものの、一時的な休職が必要になることがあります。
- 債務整理をしたら旦那にバレますか?
債務整理を司法書士に依頼した場合、任意整理であれば旦那さんにバレる可能性は低いといえます。
依頼した事務所にあらかじめご家族に知られたくない旨を伝えておけば、書類の受け渡しは直接行い、連絡方法も携帯電話やメールに限定することで、バレるリスクを最小限に抑えることが可能です。
ただし、個人再生や自己破産を選択する場合は、基本的に旦那さんの源泉徴収票や給与明細、課税証明書などの書類が必要になるため、協力が必要になるケースが多いです。
債務整理を進める際には、ご家族の理解と協力があるとより安心です。司法書士法人ライタス綜合事務所では、ご家族にも分かりやすく丁寧に説明し、手続きへの理解を深めていただけるようサポートいたします。
- 債務整理をするとクレジットカードは持てなくなりますか?
債務整理をすると、クレジットカードは基本的に使用できません。
任意整理では完済から5年、個人再生と自己破産では手続開始、または終了から5〜7年間、信用情報機関に事故情報が登録され、期間中は新規カードの作成が難しくなります。
なお、任意整理では、手続き対象の債権者を選択できるため、現在使用しているカード会社を手続きから外し、そのまま使うことも可能ですが、信用情報機関に事故情報が登録されるため、更新時の審査などで利用停止となる可能性があります。
- 債務整理をすると何が起こるのか?
債務整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録され、5〜7年間はブラックリスト状態となります。この期間中、クレジットカードの利用や新規借入れが不可能となり、携帯電話の分割払いなどに支障が生じる可能性があります。
自己破産を選択した場合、持ち家や自動車などの財産を処分する必要があり、一部の資格・職業への就業制限も発生します。
ただし、債権者からの取り立てが停止され、借金の減額や免除を受けられるメリットもあります。
- 債務整理を完済したらどうなる?
債務整理後は完済証明書が発行され、借金返済から解放されます。ただし、信用情報機関への事故情報は完済から最低5年間継続します。信用情報機関の事故情報が消えても、債務整理をした金融機関の社内情報は半永久的に残ります。
完済から5年経過後は新規借入やクレジットカード作成が可能になりますが、債務整理をした金融機関での審査は通りにくいでしょう。なお、完済後は毎月の返済負担がなくなりますが、計画的に家計管理をしていくことが大切です。
- 自己破産したらカードは作れないのですか?
自己破産後、信用情報機関に事故情報として記録され、一定期間クレジットカードの新規作成は不可能となります。期間は異なり、CIC(シー・アイ・シー)やJICC(日本信用情報機構)では約5年間、KSC(全国銀行個人信用センター)では約7年間、記録が残ります。
期間経過後は、職業や収入などの条件が整えば、クレジットカードの作成が可能です。
ただし、過去に利用していたカード会社では、破産歴が社内記録として残る場合があり、作成できない可能性があります。
- 自己破産したら銀行口座はどうなりますか?
自己破産手続きを開始すると、借入のある金融機関の口座は一時的に凍結されます。凍結期間は一般的に1〜3か月程度で、その間は預金の引き出しや各種支払いの引き落としができなくなります。また、口座内の預金は借入金と相殺される可能性があります。ただし、借入のない銀行の口座は凍結されず、新規口座開設も可能です。
給与振込や公共料金の引き落とし口座として使用している場合は、事前に借入のない銀行の口座に変更しておくとよいでしょう。
- 自己破産したら携帯はどうなりますか?
自己破産後の携帯電話の利用については、状況により異なります。
端末本体の分割払いが完了済みで、利用料金の滞納もなければ、継続利用が可能です。
ただし、利用料金の滞納があり、解消できない場合は強制解約になってしまいます。強制解約後も別キャリアであれば新規契約は可能なケースがほとんどですが、端末本体の分割払いは、信用情報機関に事故情報が登録されている5~7年間は利用が難しくなります。
- 自己破産したら車はどうなりますか?
自己破産時の車の扱いは状況により異なります。
ローンが残っている場合、所有権はローン会社にあるため引き上げられます。ローンがなくても、車の価値が20万円を超えていると、原則として手続きの中で処分されます。
一方、価値が20万円以下の車は自由財産として手元に残すことが可能です。また、20万円を超える車でも、生活に必要不可欠な場合は「自由財産拡張の申立」により保有が認められるケースもあります。
- 自己破産した借金は誰が払いますか?
自己破産により免責が認められると、借金の返済義務は法的に消滅します。誰かが代わりに返済する必要はありません。
ただし、保証人が付いている借金は、保証人が支払うことになります。
なお、税金、社会保険料、養育費、悪意による不法行為の損害賠償金などは、自己破産後も非免責債権として扱われ、支払い義務は無くならないため注意が必要です。
- 自己破産すると何が失われますか?
自己破産では20万円以上の価値がある財産が処分対象となります。
具体的には持ち家の土地・建物、価値20万円以上の自動車、ブランド品、有価証券や保険の解約返戻金が該当します。一方で、99万円以下の現金は保持することが認められていて、日常生活に必要な家財道具も処分対象外となります。
- 自己破産すると何が没収されますか?
自己破産では、原則として破産時点で所有する財産が処分対象となります。
具体的には20万円以上の価値がある自動車、株式、FX、仮想通貨、貴金属、ブランド品、退職金の一部、生命保険の解約返戻金などが処分されます。
一方で生活再建の観点から、99万円以下の現金、衣類、家電などの生活必需品は差押禁止財産として手元に残すことができます。
- 自己破産すると家族はどうなりますか?
自己破産は個人の手続きであり、家族の財産や戸籍に直接的な影響を与えることはありません。ただし、家族が保証人になっている場合は支払い義務が発生し、持ち家を失うことで引っ越しが必要になる場合があります。
また、同居家族の信用情報には記録されませんが、金融機関の審査時に不利益を被る可能性があります。家族名義の財産は原則として処分されません。家族の就職や進学、結婚に法的な影響はなく、別居している親族にも影響は及びません。
- 自己破産すると貯金はどうなりますか?
自己破産時、現金は99万円まで手元に残すことができます。
預貯金は裁判所により扱いが異なり、東京地方裁判所では20万円未満までは手元に残せます。ただし、現金と預貯金を合わせた総額は99万円が上限となります。
破産手続開始決定後に得た給与などの収入は「新得財産」として制限なく手元に残すことが可能です。自己破産前の預貯金が基準額を超える場合は、超過分が債権者への配当に充てられます。
- 自己破産は何年で消えますか?
自己破産の記録は信用情報機関により保存期間が異なります。
シー・アイ・シー(CIC)と日本信用情報機構(JICC)では約5年間、全国銀行個人信用情報センターでは約7年間記録が残ります。この期間中は新規のローンやクレジットカードの契約が制限されますが、期間経過後は信用情報から自己破産の記録が消去され、新規の借入れが可能となります。ただし、破産時の債権者であった金融機関では、社内記録として半永久的に記録が残る場合があります。
- 自己破産をしたら家族にバレますか?
自己破産が家族に知られるかどうかは状況により異なります。
同居家族がいる場合、裁判所へ家計全体の収支状況を示す書類を提出するため、知られる可能性が高くなります。家族カードを使用している場合も同様です。
一方で、一人暮らしで家族との金銭的なやり取りがなければ、知られる可能性は低いです。
- 自己破産をしたら自宅に誰か来ますか?
自己破産で破産管財人が自宅訪問をすることは通常ありません。
ただし、財産隠しの疑いがある場合、不動産などの高額財産の査定が必要な場合は、訪問することがあります。財産調査は主に預金通帳やクレジットカードの取引履歴など、客観的資料を元に行われるため、近隣に自己破産をした事実が知られる心配はありません。
個人事業主や会社経営者の場合は、事業用財産の確認のため訪問調査が実施される可能性が高くなります。
- 自己破産後何年で携帯が買えますか?
自己破産後も携帯電話の新規契約自体は可能です。
ただし、端末の分割払いについては、事故情報が信用情報機関に記録され、審査に通りにくくなるため、基本的に5〜7年間は利用できません。
この期間中に新しい端末を購入する場合は、一括払いにするか、信用情報に問題のない家族名義で契約する方法があります。なお、自己破産時に強制解約となった携帯電話会社での再契約は難しく、別の携帯会社での契約を検討する必要があります。
- 自己破産中ですがPayPayは使えますか?
PayPayは支払方法により利用可否が異なります。
チャージ式であれば自己破産中でも利用可能です。ただし、後払い方式やPayPayカードでのキャッシングは債務として扱われるため基本的に利用できません。
また、PayPayが債権者となっている場合はアカウントが凍結される可能性があり、社内ブラックリストに登録されて利用制限を受けることもあります。
- 夫が自己破産したら妻はどうなりますか?
夫が自己破産しても、妻の個人名義の財産には原則として影響はありません。妻の信用情報にも影響はなく、クレジットカードの作成やローン契約も現状通り可能です。
ただし、妻が夫の連帯保証人になっている場合は返済義務が発生し、住宅ローンなどの高額の借入が共有名義の場合は、妻も自己破産を検討しなければならないケースもあります。
- 法テラスの費用は払えません。どうしたらいいですか?
法テラスでは経済状況に応じて司法書士費用の立替制度を利用できます。
立替制度では法テラスが司法書士費用を支払い、依頼者は分割で返済することが可能です。分割払いは毎月5,000円から10,000円程度で、無利息での返済となります。手続きがすべて終了した段階で生活保護を受給している場合、返済が免除されます。
なお、司法書士法人ライタス綜合事務所でも、債務整理費用の支払いが難しい方に向け、着手金の後払い・分割払いでの対応を受け付けています。どうかお気軽にご相談ください。
- 任意整理4社でいくらかかりますか?
司法書士法人ライタス綜合事務所では、任意整理4社でご依頼いただいた場合、以下の料金となります。
基本報酬(着手金込み)176,000円(1社/44,000円)
※50,000円以下の債権の場合は、基本報酬(着手金込み)88,000円(1社22,000円)
※すべて税込み価格
なお、着手金は後払い・分割払いでの対応も可能となっていますので、お気軽にご相談ください。
- 任意整理した後にスマホの分割購入はできますか?
任意整理後は、個人信用情報に事故情報が5年間登録され、スマホの分割購入は基本的にできません。
分割払い(割賦契約)は、携帯電話会社による信用情報チェックで審査が通らないためです。対応策としては、一括払いでの購入か、信用情報に問題のない家族名義での契約が考えられます。なお、任意整理前から利用中の携帯電話は、携帯会社を任意整理の対象から除外し、料金を滞納しなければ引き続き利用できます。
- 任意整理してもローンは組めますか?
任意整理後でもローンを組むことは可能です。
ただし、任意整理の完済から5年程度は信用情報機関に事故情報が記録されるため、新規のローン契約は難しくなります。信用情報機関から事故情報が削除された後は、住宅ローンやカーローンなどの審査に通る可能性は高まります。
なお、審査通過には安定した職に就いていることや、十分な頭金を用意することが重要です。また、過去に任意整理を行った金融機関への再度の申し込みは審査に通りにくい傾向があります。
- 任意整理で借金は減りますか?
任意整理をすると、借金の将来的な利息や手数料がカットされます。つまり、元金のみの返済になるため毎月の返済負担だけでなく、最終的な支払総額も減額されます。
例えば、100万円を年利15%で借りて3年間で返済する場合、毎月の返済額は34,000円程度、支払総額は1,240,000円程になります。これが任意整理をすることで、利息や手数料がカットされ元金だけの返済になるため、毎月の返済額は27,000円程度、支払総額は借入元金の1,000,000円で完済扱いにしてもらえます。
- 任意整理にかかる費用はいくらですか?
任意整理にかかる費用は、事務所や債権者数によって変動します。
司法書士法人ライタス綜合事務所では、以下の料金となります。
・任意整理 基本報酬(着手金込み)1社/44,000円+減額した額の11%
※50,000円以下の債権の場合は、1社22,000円+減額した額の11%
※すべて税込み価格
なお、着手金は後払い・分割払いでの対応が可能となっていますので、お気軽にご相談ください。
- 任意整理の失敗例は?
任意整理の主な失敗例は以下のパターンで発生します。
返済能力が乏しく毎月の支払いが困難な場合、債権者が任意整理に応じない場合、任意整理後の返済を滞納して期限の利益を喪失する場合です。特に2回以上の滞納で一括請求を受けるリスクが高まります。また、借金額が少額で金利が低い場合や、減額分より司法書士費用が上回る場合もあります。さらに、すでに差押えを受けている状況では債権者が任意整理に応じにくく、強制執行を停止できないため失敗する可能性が高くなります。
- 任意整理の成功率は?
任意整理は債務整理手続きの中で成功率が高いといえます。
具体的な統計データは存在しませんが、債権者側にとって他の債務整理方法と比べて有利な点が多く、合意に至りやすい特徴があります。成功率が高い主な理由は、債権者が元金を回収できること、専門家による交渉機会が増えていることが挙げられます。
任意整理をご検討中の方は、司法書士法人ライタス綜合事務所にお気軽にご相談ください。
- 任意整理はよくない理由は何ですか?
任意整理は3つのデメリットがあります。
第一に、信用情報機関に事故情報が登録され、完済後も5年間はブラックリスト扱いとなり、クレジットカードやローンが組めなくなります。
第二に、任意整理後も借金返済は継続し、元金は減額されないため、安定収入がないと手続きができません。
第三に、連帯保証人がいる場合、その人に返済義務が移り、人間関係が破綻する可能性があります。
- 任意整理は何年で返済しますか?
任意整理における返済期間は、法律で明確に制限されているわけではなく、債権者との交渉によって柔軟に決定されます。一般的には3年間(36回分割払い)を目安とすることが多いですが、債務者の状況や交渉内容に応じて、5年間(60回分割払い)以上の期間が設定されることもあります。
返済方法としては、毎月1回の分割払いが一般的であり、総債務額を希望する返済期間で割った金額を毎月返済できるかどうかが、任意整理を検討する際の大きな判断基準となります。
- 任意整理は妻に内緒にできますか?
任意整理は配偶者に内緒で行うことも可能です。
郵送物は代理人である司法書士宛に送付され、債権者との連絡や和解交渉も代行してもらえます。
ただし、配偶者が保証人になっている借金が任意整理の対象である場合、手続き後は配偶者へ直接請求されるため隠すことができません。
また、クレジットカードの家族カードを使用している場合、使えなくなり発覚する可能性があります。生活用の口座が任意整理対象の金融機関の場合も、口座が止まって発覚するリスクがあります。
- 任意整理は職場にバレますか?
任意整理は、基本的に職場に知られることはありません。
司法書士が債権者との交渉窓口となり、裁判所を介さない手続きのため、会社への通知は発生しません。ただし、会社からの借入を任意整理の対象とした場合や、返済ができなくなり給与差し押さえとなった場合は、会社に知られる可能性があります。
とはいえ、バレたとしても任意整理を理由に解雇されることはないのでご安心ください。
- 任意整理は旦那に影響しますか?
任意整理が配偶者に直接的な影響を与えることはありません。
任意整理は個人の手続きであり、配偶者の信用情報に傷がつくことや、ブラックリストに登録されることもありません。ただし、家族カードが使えなくなるなどの間接的な影響が生じます。また、配偶者が連帯保証人になっている場合は、債権者から連絡が行くことになります。とはいえ、任意整理は対象債務を選択できるため、連帯保証人付きの借金を除外することで配偶者への影響を回避することが可能です。
- 任意整理を途中でやめたらどうなりますか?
任意整理を途中でやめると、債権者へ発送した受任通知の効力が失われるので、債権者からの督促や取り立てが再開され、利息や遅延損害金が全額請求されます。
その後、返済が滞ると残債務の一括返済を求められる可能性があります。
任意整理は自由なタイミングでやめられるものの、支払済みの着手金は原則として返還されませんし、信用情報機関に登録された事故情報(ブラックリスト)も削除されません。
- 面談なしで債務整理はできますか?
債務整理は原則として面談なしでは実施できません。
日本司法書士会連合会の指針により、司法書士は面談なしでの債務整理依頼の受付が禁止されています。ただし、完済後の過払い金請求のみの場合や、専門家が近くにいない地域在住、病気や自然災害により移動が困難な場合など、特段の事情がある場合は例外的に面談なしで対応可能です。
司法書士法人ライタス綜合事務所では、オンラインによる電子契約書(クライドサイン)も採用しております。どうかお気軽にご相談ください。